名城大学理工学部建築学科(第二部)卒
大工 有限会社工作舎中村建築代表
1965年生まれ
中村 武司


2025.08.05
中村 武司
名城大学理工学部建築学科(第二部)卒
大工 有限会社工作舎中村建築代表
1965年生まれ

愛知県豊田市の森の中で、名城大学理工学部建築学科OBの大工である中村武司さんが指導するツリーハウス造りが進められている。一緒に作業に取り組むのは名城大学木造建築研究会のメンバーたちだ。伝統的な木造建築工法の技術習得をめざす研究会にとって、中村さんとの月1回の作業は、学びを深める素晴らしい機会になっているという。ツリーハウス本体は一昨年夏に完成し、現在はすぐ隣の傾斜地にバイオトイレ棟を建設している。愛・地球博記念公園の「サツキとメイの家」造りの棟梁を務め、ジブリパーク造りにも関わった中村さんは、「大工の伝統の技を次世代に繋いでいきたい」と語る。

2024年1月1日に発生した能登半島地震。中村さんは1月3日、石川県七尾市の創業100年近い老舗醤油店3代目店主の鳥居正子さんから、「応急措置が必要だが頼むところがない。やっていただけませんか」という電話を受けた。中村さんの奥さんと鳥居さんは古い友人同士だった。必要と思われる復旧用資材を用意し、中村さんは1週間後の10日、支援の食糧も積み込んだトラックで現地入りした。
国の登録有形文化財にもなっている建物は、外壁がはがれ落ち、ゆがむなど大きな被害が出ていた。中村さんは2泊して、シートを張り、応急補強を終えたが、醤油の製造に欠かせない醸造蔵と、もろみを育てる室(むろ)小屋の2棟を造り替える必要があった。
鳥居さんからの正式な依頼が3月にあり、中村さんは弟子の丹羽広大さん、松木直人さんとともに、2棟の再生工事に取り掛かった。仲間の大工にも声をかけ手伝ってもらった。既存の使える用材はできるだけ使うというのが中村さんの貫いてきた方針だ。ワイヤーで引っ張って、蔵の傾きを直し、柱や梁など主だった構造材は再利用する予定だった。しかし、6月、工事の計画が変わった。壁土と屋根土を全部落としてみると、湿気で木造のフレームがいたる所で腐っていた。「すが漏れ」 といって、屋根に積もった雪や氷が接合部から浸み込み、長い年月を経て腐食していたのだ。
家は土台が命。骨組を補強するため、100年近く前に造られた石の基礎の周りをコンクリートで固め、強度を上げることにした。使える木材を愛知県日進市にある工房に持ち帰り、加工した。工房では二人の弟子により30分の1の模型が作られ、納まり具合を随時確認した。
地震発生から1年にも満たない12月、中村さんらの仕事は終わり、醤油蔵は復活した。中村さんの大工人生をドキュメンタリー番組「どえらい大工」として長期取材していた東海テレビはこの時の現場も収録していた。番組は2025年3月に放送された。工事終了のシーン。「家を建て、希望をつくる」という名古屋出身の俳優滝藤賢一さんのナレーションに続いて、「今日は本当に手を合わせました。この日を待っていました」と鳥居さんの感謝の言葉が続いた。
中村さんが名城大学に入学したのは愛知県立熱田高校を卒業して3年目の1986年。2年間浪人したわけではない。大阪芸術大学芸術学部建築学科、三重大学工学部資源化学科にそれぞれ1年弱の在学を経ての入学だった。「芸大に入ったのは美術も好きだったこともありました。2年目は三重大と一緒に名城大も受かっていましたが、若気の至りというか、なかなか方向が定まりませんでした」。
実家は祖父の代から続く大工。その祖父が40代で他界したあと、父親は中卒後たたき上げで自分の店を構えた。中村さんは3人の姉妹に挟まれた一人息子。小学校では野球部、中学、高校時代は軟式テニス部だった。大工として働く父親の背中を見て育ったこともあり、3回目の入学となった名城大学理工学部建築学科は夜間の二部を選び、昼は父親の仕事を手伝った。
授業は夕方5時半から9時ごろまで。入学した1986年、天白キャンパスでは現在の附属図書館が開館したばかりで、中村さんは時間があると入り浸った。4年生から始まるゼミは一部、二部一緒に行われたが、中村さんの思い出の一つは公益社団法人日本建築家協会(JIA)東海支部主催の設計コンペで佳作に選ばれたことだ。テーマは「幻想都市の幻覚の家」。「アートっぽいテーマへのイメージを膨らませて仕上げました」と中村さん。
牛山勉教授らから設計を学んだ中村さんは、卒業作品も、学内優秀作品(一部、二部各1人)に選ばれ、全国の大学建築学科の優秀作品集に掲載された。「大学での建築の学びはやれたかな」という達成感とともに中村さんは卒業した。
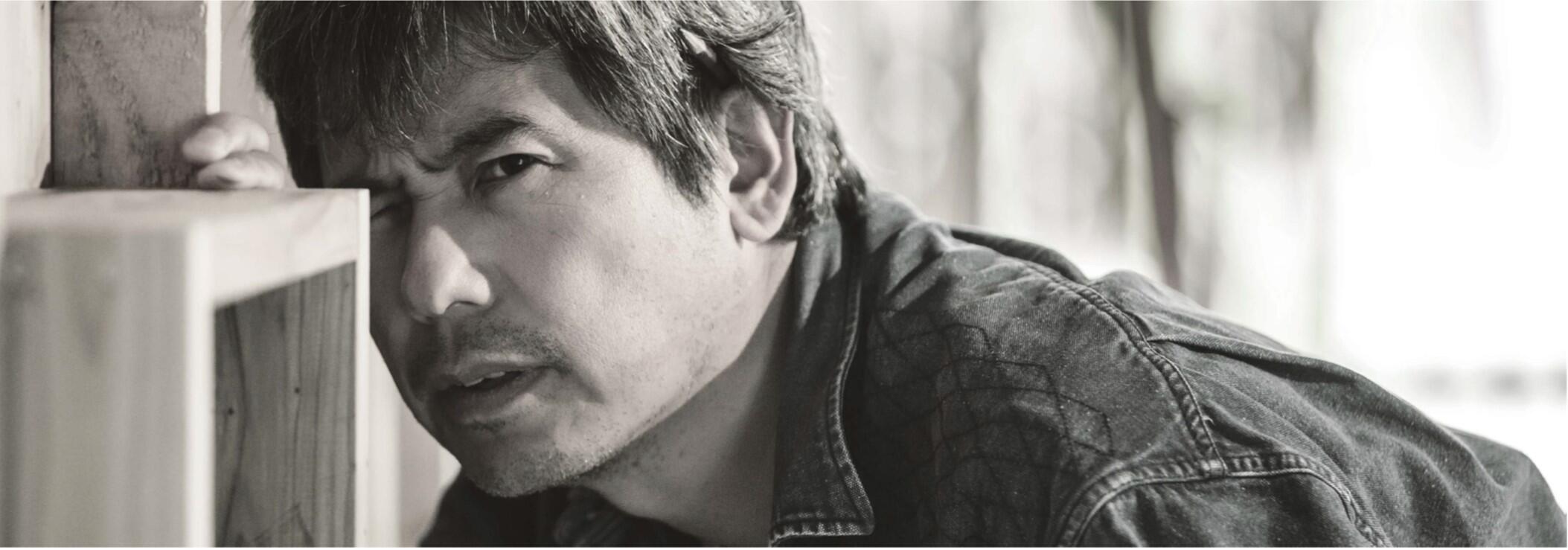

名城大学を卒業し、一級建築士となった中村さんは、そのまま父親の仕事を手伝った。ただ、個人事業主として客からの注文をこなす父親の仕事の範囲に物足りなさを感じていた。「普通の家を建てるのがつまらないというのではなく、もっと広い建築の世界があるはずだと思った」。
中村さんは卒業した1990年から、毎年夏岐阜県飛騨市で開催されている合宿セミナー「高山建築学校」や、月1回、東京で開かれる勉強会「日本建築セミナー」などの「大工塾」に参加し続けた。
また、伝統的な木造建築をより深く学ぶきっかけとなったのは、「大工塾」やその前身である「建前学校」という勉強会だった。継手(つぎて:2つ以上の部材を接合するための部品や接合方法)、仕口(しぐち:2本以上の木材を角度で、組み合わせるための合わせ目の構造)など、木組みを学ぶ実践の場だった。家業の仕事の範囲だけでは積めない経験を重ねた中村さんは、群馬、埼玉、福島、東京、長野など全国に足を運び、金物に頼らない伝統的な木組みの技術を身につけるとともに、全国の若い大工たちとのネットワークも広げていった。「面白い仕事ならどんなに遠くでも駆け付けたい」という大工たちとも出会った。大学の建築学科のカリキュラムでは学べなかった木造建築の知識は新鮮だった。

愛知万博(愛・地球博)開催2年前の2003年暮れ、中村さんのもとに、博覧会協会催事グループ「サツキとメイの家」担当部署の職員から「相談に乗ってほしい」という電話があった。名古屋駅近くの協会事務所に出向くと、待っていたのは現在株式会社スタジオジブリ取締役でアニメーション映画監督である宮崎吾朗さんだった。「映画のセットではなく、昭和30年代の家を建ててほしい」という依頼だった。
「私が『職人がつくる木の家ネット』や『大工塾』などで伝統的な木造建築に関わっていることが、雑誌やネットで紹介されていたこともあったのでしょう。博覧会協会が、この地方でそういう家を建てられる大工さんを探していて、私に白羽の矢が向けられたのだと思います」。
宮崎さんは、中村さんに制作を依頼した理由を、東海テレビ「どえらい大工」でのインタビューで振り返っている。「愛知万博は環境万博と呼ばれていた。昭和30年代くらいの暮らしに戻ればかなりエコなんじゃないかと思ったんです」。
「サツキとメイの家」を建てるにあたって、苦労したのは素材の調達だった。例えば、昭和の時代はゆがみのあるガラスが使われていたが、技術の発達で今では製造されていない。解体現場を回って捨てられる直前の物をもらったり、知り合いの大工を頼って何とか集めた。
その後、「サツキとメイの家」が縁で、中村さんは、長久手市の愛・地球博記念公園内にある、「スタジオジブリ」の世界を表現した公園施設「ジブリパーク」(2022年11月開園)の木造建築にも棟梁として関わった。「地球屋」、「猫の事務所」(青春の丘)、「どんどこ堂」(どんどこ森)などだ。
木造建築はしっかり手入れをすれば寿命は長い。中村さんは「サツキとメイの家」のメンテナンスも20年間続けている。


豊田市の森で進められている、名城大学理工学部のサークル「木造建築研究会」の学生たちも加わったツリーハウス造りが、2023年夏に完成した。そして今付属屋であるバイオトイレ棟を建設中だ。場所は同市東萩平町の安藤征夫さん所有の裏山。周囲には丸太の滑り台、巨木につるされたブランコ、40mのロープスライダーもある。
安藤さんも名城大学の卒業生(1976年商学部卒)でワンダーフォーゲル部OB。豊田市役所を早期退職して地元の建設会社社員に。まちづくり活動に取り組み、移住者用の空き家紹介や、自然を活用した子供たちの育成活動に取り組んできた。2014年からは「ガキ大将養成講座」を開いている。中村さんは安藤さんの依頼で、木造建築研究会の学生たちを指導しながら、桜の木に支えられたツリーハウスづくりに取り組んできた。
木造建築研究会(部長・谷田真准教授、2025年度会員86人)は、月1回、伝統的な木造建築を学ぶ機会として技能講習会を開催。学外活動とし、中村さんの指導で、豊田市でのツリーハウス造りに取り組んでいる。研究会ホームページの活動報告には「ツリーハウスでは、実際に大工として働いている方と一緒に作業する機会があり、より深い学びができる素晴らしい機会になっています」と、中村さんへの感謝の思いが綴られている。
中村さんには愛知産業大学(岡崎市)の招聘教授の肩書もある。2010年ころから造形学部建築学科の学生たちに伝統的な木造建築技術を教授しており、2025年日本建築学会教育賞(教育貢献)受賞者の一人にも選ばれた。
中村さんは、「私が学生だったころは、大学で木造建築とか実際のモノ造りに接する機会はなかったが、最近は建築教育の中で、体や手を使ってモノづくりの学びを体験する試みが増えてきている。私の歩んできた道も正解だったかなと思っています」と嬉しそうだ。


中村さんは父親が持っていた愛知郡東郷町の50坪の土地に2010年、木造2階建ての自宅を建てた。兵庫県で開催された、貫(ぬき:柱を貫通するように水平に通された木材)・土壁で造られた伝統工法の家屋の耐震性を調べる実験に参加した際、使用した建材が再利用者希望者に提供されると知り手を挙げた。実験に耐えた建材を使った家で、実際に生活してみようと思った。国交省から、わずかだが助成金も受けて建てた家で、家族4人で暮らしている。中村さんは、「住んでみて全く問題はありません。能登の地震でも経験しましたが、傾いたから壊そうではなくて、直せば十分再利用できることのPRに少しでも役立てばと思っています」。
名古屋市昭和区から東郷町に移り住んだ中村さんは、息子たちを通して関わるようになった地元の和太鼓伝承など新たな地域活動にも参加。同町のNPO法人「ノーマCafe」の理事として、町内の雑木林に秘密基地をつくる「わんぱく族」の指導もしている。東郷町だけでなく、依頼された各地の小学校や中学校、高校などでの野外体験学習、探究学習にも講師として足を運ぶ。
中村さんが名城大学で学んだ4年間の大半は昭和の時代だった。中村さんは昭和の時代を知る世代としての使命感があるという。
「昭和という時代は単なるノスタルジーではありません。なにか置き忘れてきている面もあるのではないかと思います。それを知っている世代が、しっかり次の世代に渡していかないと、大切なつながりが途絶えてしまう。建築も、建築以外のコミュニティーもそうです。全てがリレーのバトンだと私は思っています。大工という立場、高校生と大学生の子を持つ親の立場で、持っているバトンを次の世代や子どもたちに確実に渡したいと思っています」。