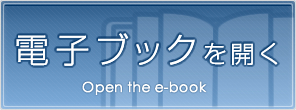名城大学通信 44 [2012 summer] page 9/44
このページは 名城大学通信 44 [2012 summer] の電子ブックに掲載されている9ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
MEIJO HEAD LINE NEWS私立大学戦略的研究基盤形成支援事業で2プロジェクトが始動研究プロジェクトニュース文部科学省の平成24年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の「研究拠点を形成する研究」に、本学から2つの....
MEIJO HEAD LINE NEWS私立大学戦略的研究基盤形成支援事業で2プロジェクトが始動研究プロジェクトニュース文部科学省の平成24年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の「研究拠点を形成する研究」に、本学から2つの研究プロジェクトが採択されました。理工学研究科の赤﨑勇教授(半導体物性工学)を代表とする「窒化物半導体・新領域エレクトロニクス」と、理工学研究科の小高猛司教授(地盤力学)を代表とする「21世紀型自然災害のリスク軽減に関するプロジェクト」です。私立大学戦略的研究基盤形成支援事業は、私立大学が、各大学の経営戦略に基づいて行う研究基盤の形成を支援するため、研究プロジェクトに対して重点的かつ総合的に補助を行う事業です。研究グループの4人。右から竹内准教授、赤﨑教授、上山教授、岩谷准教授。界最短波長半導体レーザ、高効率紫外ロニクスの実現を目指します。体による青色/紫色LEDをはじめ、世持続発展社会に必要な新領域エレクトをベースに世界に先駆けて窒化物半導究極的な性能をもつデバイスを開発し、の実現と伝導性制御を達成し、その技術さらには他材料との融合デバイスなど、は、世界で初めて同材料の高品質単結晶電池の3倍)、面発光レーザ(未踏領域)、﨑教授を代表とする同研究グループで換効率60%の太陽電池(現状のSi太陽ど応用分野が急速に拡大しています。赤の革新の両面から克服し、エネルギー変パネル(ディスプレイ)のバックライトなを、結晶成長の革新とデバイスプロセス有していることから、種々の照明や液晶本研究プロジェクトでは、これらの難題小型・高効率・長寿命など優れた特長を化領域拡大の大きな障害になっています。窒化物半導体による白色LEDは、ルの一部を利用しているに過ぎず、実用窒化物半導体がもつ物性的なポテンシャ新領域エレクトロニクス」伝導性制御が極めて困難であり、いまだ「窒化物半導体・整合のため、高品質混晶の作製や混晶の革新的なデバイスを目指すしかし、本材料系固有の大きな格子不物性ポテンシャルを活用し、を実現してきました。窒化物半導体がもつ未発現のLEDなど数々のフロンティアデバイス「21世紀型自然災害のリスク軽減に関するプロジェクト」を推進するテーマリーダー5人。前列右から小高教授、原田教授。後列右から柄谷准教授、葛教授、武藤教授。よる沿岸域低平地の自然災害リスク軽ロジェクト始動への意欲を語っています。科教授)④水工学地盤工学の連携に-する研究に取り組んでいきたい」と大型プする研究(原田守博・建設システム工学て、21世紀型の自然災害のリスク軽減に関事象の発生機構とリスク軽減方策に関な研究だけでなく、ソフト的な対策も含め藤厚・建築学科教授)③豪雨および水災うとらえるかが非常に重要です。ハード的安全性評価による震災リスクの軽減(武して起こります。そうした連動現象をどム工学科教授)②大空間構造物の耐震きな災害が起きると、いろんな現象が連動の向上に関する研究(葛漢彬・建設システ小高教授は、「東日本大震災のような大震に対する土木構造物の安全性と修復性同研究体制となります。各テーマとリーダーは①連動型巨大地を中心にした教員も加わり計19人での共は5つの研究テーマで構成されています。境創造、建築)と都市情報学部から若手災害のリスク軽減に関するプロジェクト」かに理工学部3学科(建設システム工、環小高教授を代表とする「21世紀型自然ロジェクトには5人のテーマリーダーのほ明(柄谷友香・都市情報学部准教授)。プ「軽減2119世人に紀の関型共す自同る然研プ災究ロ害でジェのクリスクト」被災限界からの自律再建メカニズムの解科教授)⑤「中核被災者」を主体とした減への挑戦(小高猛司・建設システム工学08 44
![名城大学通信 44 [2012 summer]](../books/images/t/g_9.jpg)