Learning Beyond Words: Experience at a Philippines Orphanage
教員免許状取得を目指し、教職課程を履修している黒﨑梓里さん。生徒と心を通わせられる教員になるためにコミュニケーション力を身につけたいと、フィリピン・セブ島の孤児院でボランティアをする海外研修プログラムに参加しました。日本を飛び出した先で得られた学びとは?
孤児院ボランティアで子どもたちの心の機微に触れたい

生物資源学科では、栽培植物の生産技術や微生物、自然環境との関わりについて学んでいます。同時に教職課程を履修していて、高等学校の理科と農業の教員免許状取得を目指しています。
将来は農業高校の教員になりたいと思っていますが、教壇に立つ自信を持てずにいました。なぜ自信がないのか掘り下げてみると、私は人の気持ちや感情を理解したり、自分の思いを伝えたりするのが苦手だからです。感情のやり取りが苦手なままでは、生徒の心に寄り添える教員にはなれないと思いました。
コミュニケーション力を磨くにはどうしたらいいだろうと考えていたときに、たまたま大学のキャンパスで目にしたのが、フィリピン・セブ島での海外ボランティアプログラムのチラシでした。プログラムには、セブ市内にあるNGO施設の孤児院でボランティアをするコースがありました。孤児院でボランティアをすれば子どもたちと近い距離で接し、コミュニケーションを深めることができるのではないかと思って参加を決めました。また、教職課程で愛着障害について学び、障害特性を理解することは、将来さまざまな生徒と接する上で必要だと感じていたので、孤児院でのボランティアは良い機会になるだろうと考えました。
元気で人懐っこいセブの子どもたちと過ごす時間

語学に自信があったわけではないので、ボランティアに参加するにあたって必要になりそうな英単語を覚えたり、名城大学が提供している無料の英会話レッスンを利用したりして準備しました。ただ、コミュニケーションツールは言語だけでなく、ジェスチャーや表情、声色などいろいろあります。日本を飛び出して言葉だけに頼らないコミュニケーションを経験することで、学べることがあるのではないかという期待もしていました。
セブでの滞在は15日ほど。その間、週末以外は毎日孤児院に通いました。孤児院の中に幼稚園があり、ボランティアスタッフは幼稚園で先生たちの補助をし、幼稚園が終わった後は、孤児院で暮らす子どもたちと交流するのが日課でした。
フィリピンの孤児院には、愛情はあっても経済的に苦しい家庭の子など、さまざまな背景をもつ子どもたちがいました。とはいえ、みんな驚くほど人懐っこくて元気。子どもたちから「遊ぼう、遊ぼう」と、左右の腕を強引に引っ張られて困っていたときは、現地のスタッフの方から「まずは子どもたちの話を聞いて落ち着かせてから、『順番だよ』と説明してあげるといい」とアドバイスしていただきました。アドバイス通りに接してみると、みんなちゃんと理解して順番を待ってくれるようになり、あらためて子どもの目線に立って接することが重要なのだと気付かせてもらいました。
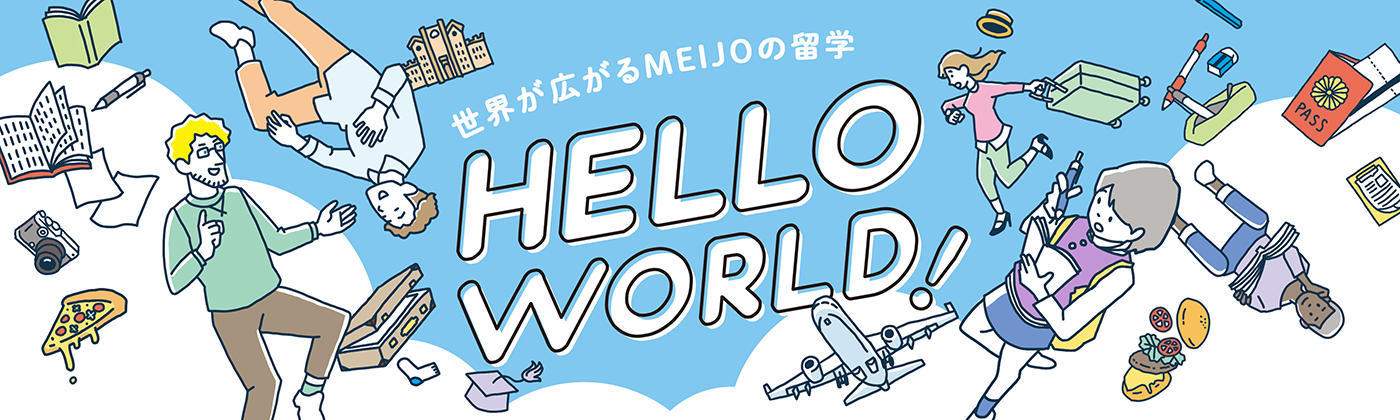
コミュニケーションには言葉よりも大切なことがある

言葉の面で、いくつか苦労することもありました。子どもたちが一生懸命英語で話しかけてくれるのですが、何を言っているのか理解してあげられず、子どもたちが不貞腐れてしまったり、子ども同士が喧嘩していた際に、喧嘩の原因がよく分からなくてうまく仲裁してあげられなかったり。
それでもコミュニケーションを諦めず、その子が落ち着くまでそばにいて、声をかけるようにしていました。そうすると、不貞腐れていた子も少しずつ笑顔を見せて、懐いてくれるようになったのです。例え言葉が通じなくても、「あなたのことを気にかけているよ」「理解しようとしているよ」という思いが伝わったことで、心を開いてもらえたのだと思います。
セブの子どもたちが心を開いてくれたことは、コミュニケーションに不安を持っていた私にとって自信になりました。最初は緊張していて、子どもたちとどう接したらいいのだろうと考えを巡らせてばかりいたのですが、変に考えすぎず、目の前の相手に関心を持ち、理解しようとする姿勢を見せれば、心を通わすことができるのだと身をもって体験しました。
生徒の気持ちを理解し、寄り添ってあげられる教員に
私が教員を目指すようになったのは、高校生のときに出会った先生のおかげです。クラスに馴染むことができなかったときに、いつも声をかけてくれて親身に話を聞いてくれました。怒られたこともたくさんありましたが、心配してくれている気持ちが伝わってきて嬉しかったのを覚えています。
農業高校だったのですが、先生から提案されてアメリカ、ブラジル、ドイツ、オランダを巡る農業高校生向けの海外実習に参加しました。先生も高校生のときに参加したのだそうです。そのときの経験があったので、今回も海外でのボランティアプログラムに躊躇なく参加することができました。私も教員になったときには、自分の国際交流経験を生徒に積極的に伝えて、背中を押してあげられる存在になりたいです。
4年生になると教育実習がありますが、今は楽しみ半分、不安半分です。楽しみなのは、生徒たちとのコミュニケーション。セブでの経験を生かして、教育実習でも生徒たちとしっかりと向き合って、表面的ではないコミュニケーションで信頼関係を構築したいです。不安なのは、ちゃんと授業ができるだろうかということ。まだ模擬授業なども経験がないので心配ですが、教職課程を履修する中で、知識と経験を増やして自信をつけていきたいです。そして将来は、私が憧れた先生のように、一人ひとりの生徒に寄り添い、親身になってあげられる教員になるのが目標です。
-

一緒にプログラムに参加した名城生との集合写真。孤児院ボランティア以外に、学校やホテル、空港でインターンシップをする学生もいました
-

現地セブのインターンシップ生たちと。孤児院で一緒に働き、仲良くなりました
-

孤児院では、幼い子から高校生まで多様な子どもたちが暮らしていました。またいつか、会いに行きたいです
-

週末はアクティビティに参加。アイランドホッピングをして、水上バイクにも挑戦しました
-

セブの路上で売られていたココナッツウォーター。甘さ控えめで、さっぱりとしていました
-

シーフードを手づかみで食べる「バケットシュリンプ」は、セブのローカルフード。程よくスパイシーでおいしかったです
MESSAGE

海外ボランティアプログラムのチラシを見て、勢いで申し込みをしましたが、フィリピンの現状を知ることができ、不安だったコミュニケーションにも少し自信を持てるようになり、得るものはたくさんありました。行こうかどうか悩んでいても、きっと不安が募るだけ。考えすぎずに、勢いに任せて行動してしまうのもありだと思います!
留学DATA
| プログラム | 令和6年度春期 海外ボランティア・インターンシップ in セブ |
| 派遣期間 | 2025年2月1日(土)〜2025年2月15日(土) |
| 研修地 | フィリピン・セブ島 |
COPYRIGHT © MEIJO UNIVERSITY, ALL RIGHTS RESERVED.


