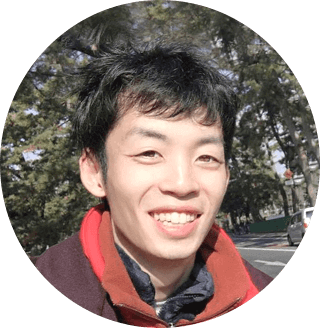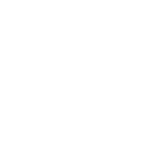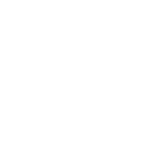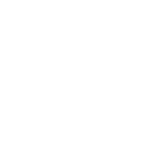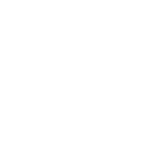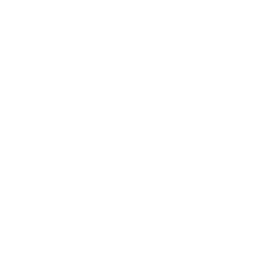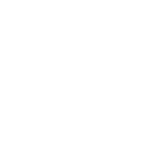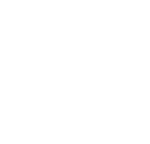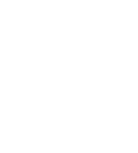プロジェクトリーダー
外国語学部 3年 長江 はるかさん
PROJECT START
学生生活、悔いのないよう思い立ったらすぐ行動!
大学3年生になった時、ふと、この学生生活で「やり残したことがないか?」と頭をよぎりました。
いても立ってもいられない私は、ずっと抱いていた郷土”愛知”の魅力を発信したい気持ちもどんどん大きくなっていき「これだ!」と決断。取材費のサポートなども受けられるEnjoy Learningプロジェクトにチャレンジするには時間がかかりませんでした。
WHAT WE LEARNED #01
「魅力がない街」愛知県の
隠れた魅力を発信したい。
愛知県は「魅力がない街」と呼ばれることがありますが、愛知在住のメンバーにとっては多くの魅力に溢れた街です。汚名の原因は、愛知県自体の問題ではなく、魅力あるコンテンツを上手く発信できていないことだと感じました。それらをゼミの教授に雑談の中で相談したところ、このEnjoy Learningの制度を教えてもらい、仲間を集めて愛知県のPR活動にチャレンジすることになりました。


WHAT WE LEARNED #02
現地に赴くことで体で感じ、
リアルな情報を届ける。
地域性やイベント性を基準に投稿内容を検討し、計画を立てて撮影取材を実施します。また、県外の成功している観光地を積極的に取材することで、集客や顧客満足度を向上させるノウハウを蓄積。調べるだけでなく、実際に現地に赴くことを大切にしており、いかにリアルな内容を魅力的に発信できるかが課題です。情報に誤りがあってもいけないので、毎回現地で人物取材し、生の声を聞くようにしています。
WHAT WE LEARNED #03
海外に向けた多言語展開で
自分たちだからこその発信を。
多くのメンバーが外国語学部であることを強みに、海外への発信に力を入れています。取材の際は外国人観光客に話を聞いたり、投稿の際は複数の言語でコメント表記する工夫など。投稿に対して海外の方から反応がもらえると、やりがいに繋がります。英語だけでなく、中国語やフランス語など、展開の可能性は広がるばかり。成果を出すのはなかなか難しいですが、工夫して投稿するたびに発見があります。


プロジェクトリーダー
外国語学部 3年 長江 はるかさん
PROJECT SUMMARY
共感と意見交換が成果を生んだプロジェクト。
愛知のモノを発信したい!という漠然としていた想いを、大学に共感してもらえプロジェクトを開始できたことは大きな自信と原動力になりました。
活動を行っていくなか、世代や立場が異なる方々と各プロセスで意見交換、プレゼンをすることで多くの共感を得る事ができたと思います。結果として、届けたかった海外の方からのリアクションがあったときに「やった!やりきった!」っとメンバー全員が達成感でいっぱいでした。