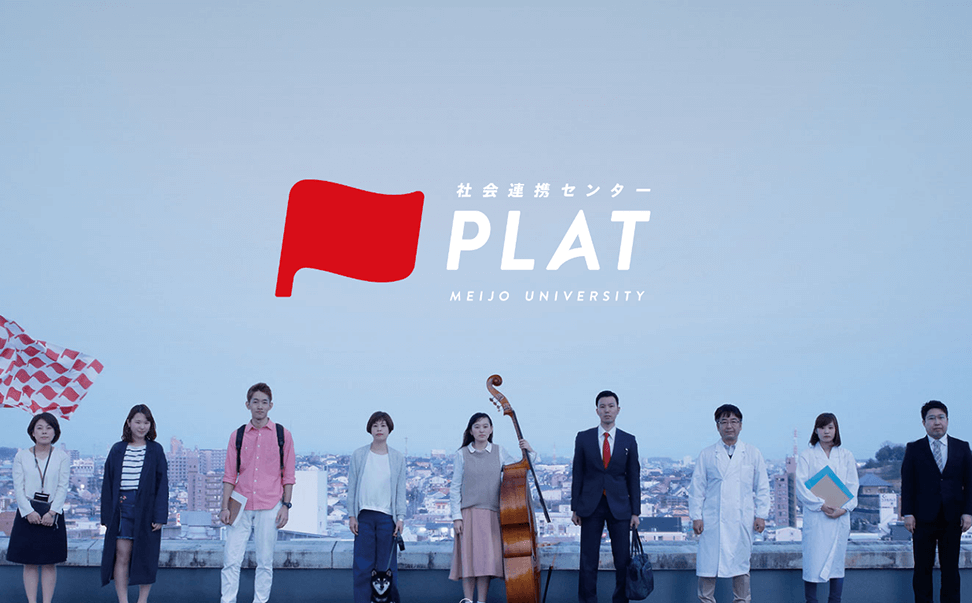特設サイト第123回 漢方処方解説(70)香蘇散
今回ご紹介する処方は香蘇散(こうそさん)です。
この処方は、虚弱者の感冒初期に用いるものとされますが、まだ風邪を引いたとも言えないくらいで、なんとなく調子が悪く、スッキリとしない、もしかして風邪かもしれないというときに効果を発揮すると考えられています。そういう点では、葛根湯や桂枝湯を飲もうかという前の状態に使われる処方です。
構成生薬は、香附子(こうぶし)、蘇葉(そよう)、陳皮(ちんぴ)、甘草(かんぞう)、生姜(しょうきょう)の5つです。香附子はカヤツリグサ科ハマスゲの根茎を用いる生薬で、α-シペロンなど精油を含み、香の濃厚なものが良品とされます。蘇葉はシソ科シソの開花期直前の葉を用いる生薬で、葉が大きく肉厚で、砕けておらず、芳香が強く、枝や柄がないものがよいとされます。また、年月の経過したものではなく、なるべく新しいものがよいとされます。陳皮はミカン科ウンシュウミカンの成熟した果皮を用いる生薬で、リモネンなど精油やヘスペリジンなどのフラボノイドを含み、外皮がオレンジ色で裏面が白くて肌の細かいもので、気味の強いものがよいとされます。こちらは新しいものでは悪心などが生じることもあり、少し年月の経過したものがよいとされています。陳皮の「陳」は「古い」とか、「時間が経過したもの」を意味しています。生薬の中では、蘇葉のように乾燥した後、比較的あたらしいものがよいとか、陳皮のように乾燥して、さらに時間が経過したものがよいとか言われるものがあり、「六陳八新」と言われています。
生薬の薬能で考えると、香附子や蘇葉、陳皮は香りのよい生薬ですから、気の巡りをよくする「理気薬」としてはたらき、その中でも蘇葉は生姜とともに発汗させる「解表薬」としてもはたらきます。甘草は甘味の生薬として生姜とともに「お腹のくすり」としてはたらくとともに、「補気薬」としてもはたらきます。全体的に、気の巡りを改善し、発汗させて発散させるものでもあり、お腹の調子も整えて、気分をスッキリとさせるものと考えられます。そのため、気分がすぐれないとか、少し塞ぎこむといった精神症状の緩和に有効です。原因がはっきりとせず、なんとなく不調というときによい処方です。
香附子は鎮静作用や駆瘀血作用ももつ生薬ですから、この処方も更年期障害や月経障害などの婦人病にも用いられます。興味深いところでは、魚などが原因で生じた消化器症状や蕁麻疹などの食中毒にも有効とされています。香附子以外、食品でもある生薬で構成されており、とても興味深い処方ですね。

蘇葉(八事キャンパス)
(2025年7月4日)