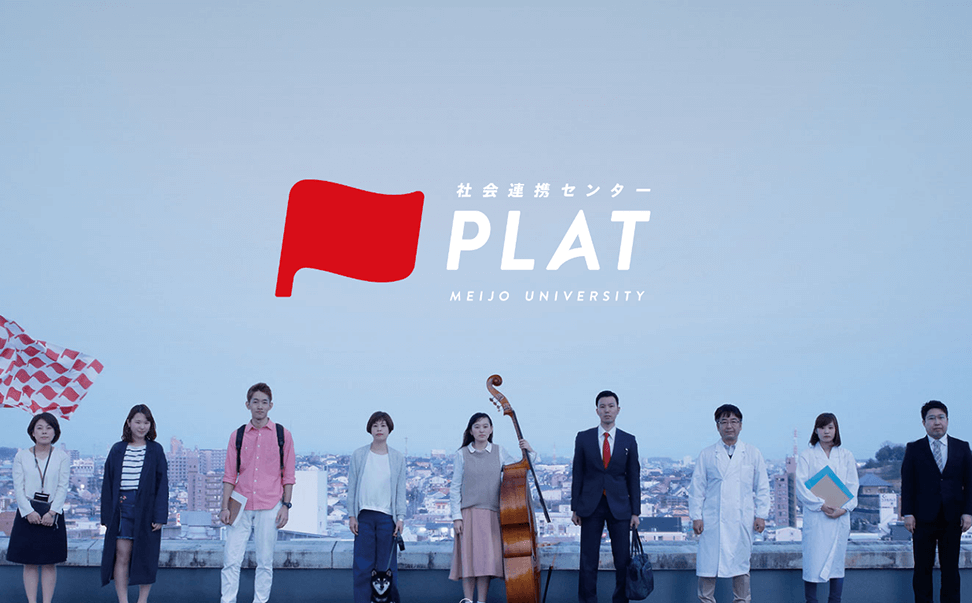特設サイト第125回 漢方処方解説(72)五淋散
9月というのに40度近い気温が続いています。昨年も暑い日が続き、暖冬なのかなと思いきや、寒さ厳しい冬となって驚いたものですが、今年はどうなるのでしょう。
さて、今回ご紹介する処方は五淋散(ごりんさん)です。尿路の炎症に用いる処方の一つで、症状があまり強くない例に使用できるとされています。
構成生薬は、出典である「太平恵民和剤局方(たいへいけいみんわざいきょくほう)」では茯苓、当帰、甘草、山梔子、芍薬の5味ですが、明代の「古今医鑑(こきんいかん)」では黄芩が加えられて6味となり、さらに地黄、沢瀉、木通、滑石(かっせき)、車前子(しゃぜんし)を配合して11味となったものが現在医療用漢方エキス製剤として利用されています。

「太平恵民和剤局方」によれば、本処方は「腎の気」が不足して膀胱に熱(炎症)が生じると尿道が通じず、結果として排尿困難となり、また排尿が少ない割には頻尿で、下腹部が痛み、尿が米のとぎ汁のようになったものを治すとか、あるいは砂のような石が混じり、排尿時の熱感はないけれど尿が出るものを治すとか、あるいは熱感があって血尿が出るものなど、すべての排尿異常を治すと記されています。また、「古今医鑑」では「腎の気」ではなく、「肺の気」が不足してと記されており、「水(津液)」を全身に循環させる「肺」の機能低下か、「水(津液)」を貯蔵することで動きを調節する「腎」の機能低下のどちらが原因であると考えるのか、当時の医学の捉え方の違いとして興味深く感じます。いずれにせよ、排尿困難、尿の混濁、尿路結石、血尿などに用いられていますが、明らかな尿路感染症が疑われる場合には抗菌剤の併用が必要なのは言うまでもありません。
その他尿路にまつわるトラブルに処方される漢方薬としては、膀胱炎の急性期に猪苓湯がよいとされますし、類方である猪苓湯合四物湯は再発性膀胱炎の予防に用いられています。また、急性期で、体質や体格が充実している方で排尿痛などの症状が強い場合には竜胆瀉肝湯がよいとされます。さらに、膀胱炎症状は軽いものの、遷延化した場合で、胃腸が虚弱な方には清心蓮子飲がよいでしょうし、高齢者で膀胱機能が低下し、残尿や失禁などの排尿障害も伴う場合には八味地黄丸や牛車腎気丸がよいと考えられています。
(2025年9月3日)