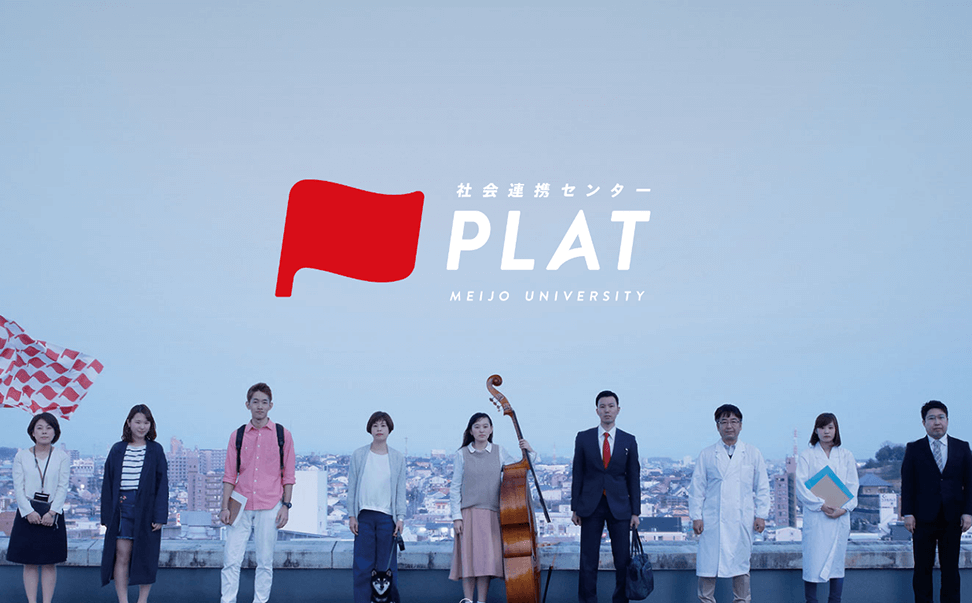学部・大学院研究科長メッセージ
MESSAGE
経済学研究科で研究を志す皆様へ
理論経済・経済史,経済政策,現代産業構造
経済学には様々な定義がありますが、人、モノ、金、さらには時間や情報といった限られた資源を、人々がより満足する生活を送ることができるように、どのように配分するのかを論理的に考える学問といえます。論理的に考えるには、理論・計量・歴史さらにはフィールドワークなどといった経済学の様々なツールを用いることになります。大学院の主要な目的は、修士論文・博士論文を作成することですが、それぞれの論文のテーマに関連するこうしたツールの高度な利用の仕方を、まずしっかりとマスターして下さい。そのために経済学研究科では、理論経済・経済史、経済政策、現代産業構造というの3つの専修分野のもとに、多くの科目が開講され、それぞれの分野の最前線で研究を行っている教員による少人数教育が行われています。指導教員以外の教員からも指導を受けることによって、自分の研究テーマをより深く掘り下げられるようになります。
論文の作成
大学院に入学する前に、修士論文・博士論文で何をテーマにするのかについては、既に考えていると思います。しかし、それを具体的な論文の形にするためには、多くの作業が必要になります。まずは、リサーチクエスチョンを設定し、それをもとに仮説を立てます。そして、仮説を検証するのですが、そのために上記の経済学のツールをフルに活用することになります(もちろん、仮説を立てるのにも活用されます)。ここで大切なことは、仮説が間違っていても、それを受け入れることです。自分で立てた仮説にこだわりすぎで、都合のよい事例ばかりを集めるのではなく、現実を真摯に見つめて、仮説を修正し、再検証することも必要になりますし、なぜ仮説が成立しないのかを考え、そこからインプリケーションを導き出すことも重要な意味をもつはずです。
そうした過程で、自分の思ったように研究が進まず、行き詰ることもあると思います。こうした作業を一人で行うのではなく、指導教員はもとより、関連する科目担当者、あるいは経済学研究科の学生の意見も聞きながら、壁を乗り越えて下さい。そうした指導体制・研究環境が、経済研究科には整えられています。
研究科長 佐土井 有里