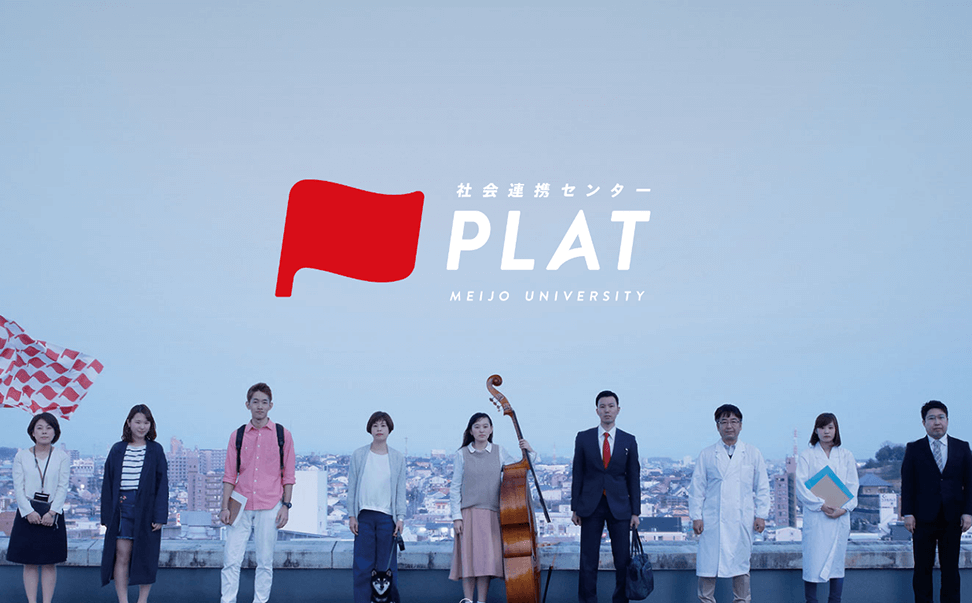トップページ/ニュース 防衛大学校の河野仁教授が都市情報学部で講義
演題は「軍隊と社会-軍事組織におけるジェンダー統合の歴史-」
 登壇した防衛大学校の河野教授
登壇した防衛大学校の河野教授
防衛大学校人文社会科学群公共政策学科の河野仁教授(軍事社会学)が7月9日、本学都市情報学部の稲葉千晴教授が担当する3年次開講科目「都市と国際関係」でゲスト講師として登壇。学生約80人に「軍隊と社会-軍事組織におけるジェンダー統合の歴史-」をテーマに、日本の自衛隊をはじめとする軍隊での女性兵士の活用の国による違いやその歴史的変遷などについて解説しました。
ソ連には女性の狙撃兵や戦闘機パイロットの存在も
-
 講義の様子
講義の様子
-
 米国の女性兵士の歴史を解説
米国の女性兵士の歴史を解説
河野教授は初めに前提として、1970年代に使用されるようになった「ジェンダー」(文化的・社会的に構築された性差の概念)と「フェミニズム」(女性の自由・平等・人権を求める思想)について解説。「フェミニズム第一期(19世紀末から20世紀初め)は参政権を求め、政治的目的を達成すると、1960年代以降の第二期は『ウーマン・リブ運動』に代表されるように男女の実質的な平等を求めた」と説明しました。
そのうえで河野教授はまず、第二次世界大戦時の各国のジェンダー戦略(ジェンダー・ダイバーシティに配慮した人材の活用)について、日本やドイツなど当時の枢軸国では「男は前線、女は銃後」などと性別で役割が分担されている「ジェンダー分離型」戦略、米国や英国など連合国は補助部隊など後方任務にとどまるものの女性も兵士としての役割を持つ「ジェンダー参加型」戦略だったと解説しました。
その中で、ソ連については「女性も戦闘任務に就き、戦闘機パイロットや女性だけの爆撃連隊、スナイパー(狙撃兵)も存在し、全兵力の8%に当たる100万人の女性兵士が従軍していた」。一方、日本については「軍国の母や妻としての役割が重視されていたため、女性は通信隊など正規の軍人ではない軍属や戦争末期には竹槍を持つ民兵としての役割にとどまった」と説明しました。
学生たちに「男女平等徴兵制法案に賛成? 反対?」を問う質問も
続いて河野教授は、冷戦後のヨーロッパや米国など各国軍のジェンダー統合の歴史をひも解き、2000年に国連安全保障理事会がジェンダー平等の視点をすべての政策・施策・事業に組み込む「ジェンダー主流化」の促進をうたった決議を行い、2007年にはNATO軍女性委員会が「ジェンダー主流化促進の手引き」を承認したことを解説。これにより「軍隊に女性がいた方が作戦の効果が高まるという認識を得るようになった」と指摘しました。
河野教授は特徴的な事例として、ロシアからの脅威が高まっている北欧ではノルウェーが2015年から女性の徴兵制を、スウェーデンも2017年に男女平等の徴兵制を導入したことや、米国では今年に入って第二次トランプ政権の「反DEI(多様性・公平性・包摂性)政策」により米軍内の女性や黒人の将官が次々と解任されたことなども解説。さらに、自衛隊のジェンダー統合の歴史を概説した研究書の内容も紹介しました。
講義の最後には、河野教授は学生たちに「X国の国会議員になったとして、提案された男女平等の徴兵制法案に賛成か反対か」を問う質問を投げかけました。これに対し、賛成とした学生は「軍隊の仕事も女性でも十分に活躍できる仕事があるから」「人口の減少が続いており仕方がない」といった理由を説明。反対の学生は「ドローンなど最新兵器を使うことで、できるだけ人を使わないようにすればいい」などと答えていました。
-
 ソ連の女性兵士について解説
ソ連の女性兵士について解説
-
 河野教授教授を紹介する稲葉教授(右)
河野教授教授を紹介する稲葉教授(右)