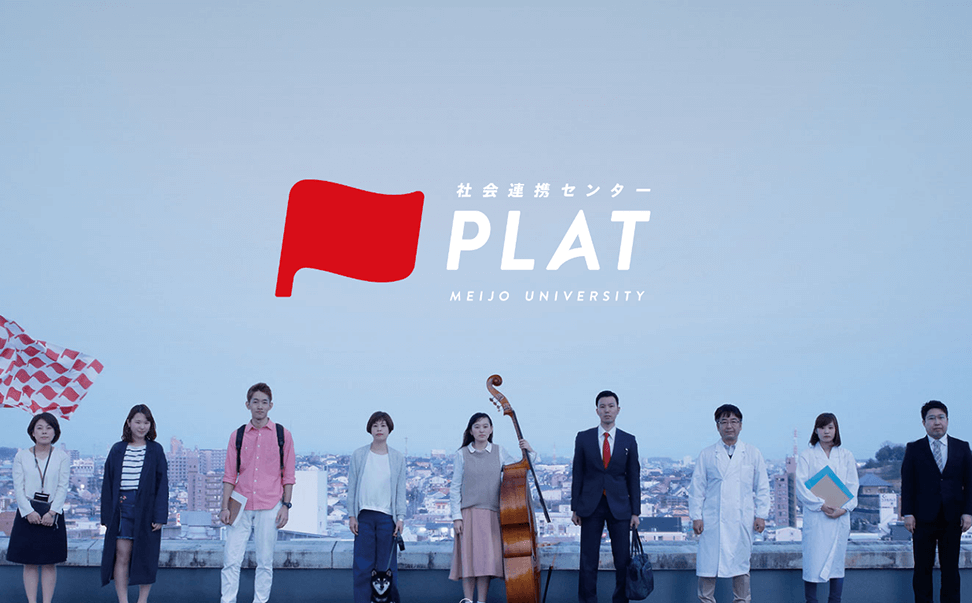トップページ/ニュース 経営学部の相川奈美教授のゼミ生が防災カードゲーム「なまずの学校」とSOMPO流「逃げ地図」づくりを体験
損保ジャパンとの「昭和区防災・減災秋まつり」(11月)での共同出展に向けて
 SOMPO流逃げ地図」づくりワークショップを体験するゼミ生
SOMPO流逃げ地図」づくりワークショップを体験するゼミ生
経営学部の相川奈美教授のゼミと「損害保険ジャパン株式会社」(損保ジャパン、本社・東京都新宿区)が協働して、名古屋市昭和区の川名公園で11月8日に開催される「昭和区防災・減災秋まつり」に産学連携プロジェクトとして共同出展することになり、天白キャンパスのタワー75レセプションホールで7月14日、出展内容を検討するため、損保ジャパンが開発した防災カードゲーム「なまずの学校」などを学生たちが体験しました。
災害時のさまざまなトラブルの解決方法を考える防災カードゲーム「なまずの学校」
-
 防災カードゲームを実践
防災カードゲームを実践
-
 防災カードゲームの答えを考える
防災カードゲームの答えを考える
体験会にはゼミの2、3年生28人と損保ジャパンの社員4人が参加。学生たちは損保ジャパンの社員の説明を聞きながら、損保ジャパンが展開する「防災ジャパンダプロジェクト」の防災ワークショップのうち、防災カードゲーム「なまずの学校」と、認定NPO法人日本都市計画家協会に設立された「逃げ地図研究会」に損保ジャパンが参画して普及に努めているSOMPO流「逃げ地図」づくりワークショップを体験しました。
初めに取り組んだ「なまずの学校」は、地震などの災害で起こるさまざまなトラブルの解決方法を考えるワークショップです。紙芝居形式で「下敷きになった人を助けるのに使えそうなものは?」といったクイズを出題し、「ジャッキ」「バール」「のこぎり」「フォークリフト」といったアイテムのカードの中から、そのトラブルを解決するのに最もふさわしいと思うアイテムのカードを選び、ポイントの合計点を競います。クイズは実際に阪神大震災などの被災者へのヒアリングやアンケートを基にして作られています。
この日の体験会ではスライドでクイズが2問出題され、このうち「何を持ち寄って火を消せばいいか?」との問いには、学生たちは映し出された「水」や「消火器」「可搬式ポンプ」「コンビニ袋」「バケツ」のカードから選んで回答すると、損保ジャパンの社員が「すぐ手に入って使いやすいのは『バケツ・コンビニ袋』です」と最も高得点のカードとその理由を説明。さらに「阪神大震災でもバケツリレーが役立ったので、皆さんも覚えておいてください」と呼び掛けました。
避難の際に危険な場所や逃げる方向などを理解するSOMPO流「逃げ地図」づくり
続いて取り組んだワークショップの「逃げ地図」とは、大雨などの災害時に目標とする避難場所まで歩いてかかる時間を色鉛筆で塗り分けるなどして手作りした地図で、危険な場所や逃げる方向を理解することができます。SOMPO流「逃げ地図」づくりワークショップでは、参加者が話し合いながら地図を作ることで、地域の課題の発見につながったり、参加者間のコミュニケーションの促進にも役立ったりする効果もあります。
学生たちは5班に分かれ、水害を想定して地図づくりをスタート。まず天白キャンパス周辺のハザードマップをもとに白地図に避難所に適した安全な場所をシールで印をつけ、その避難所への移動にかかる時間によって周辺の道路を緑や黄緑、黄色と色鉛筆で塗り分けていき、橋などの通行できなくなる場所には「×」を書き込みました。初めは「難しい」と戸惑っていた学生たちも、損保ジャパンの社員のアドバイスを聞いて「ここは崖が崩れそうな場所」「川沿いで避難が難しそう」などと話し合って地図づくりを進めていました。
この後、学生たちは損保ジャパンが制作し、持続可能な社会への道のりをゲーム感覚で学ぶことができるオリジナルの「SDGsカード」を使ったカードゲームも体験しました。相川ゼミでは今後、この日の体験で得た学生たちの意見や感想をもとに、「昭和区防災・減災秋まつり」での出展内容を損保ジャパンとともに詰めていくことにしています。
-
 逃げ地図づくりでアドバイスする損保ジャパンの社員
逃げ地図づくりでアドバイスする損保ジャパンの社員
-
 班の中で話し合いながら地図づくり
班の中で話し合いながら地図づくり
-
 「逃げ地図」づくりで工夫した点を発表するゼミ生
「逃げ地図」づくりで工夫した点を発表するゼミ生
-
 損保ジャパンの取り組みなどの紹介
損保ジャパンの取り組みなどの紹介