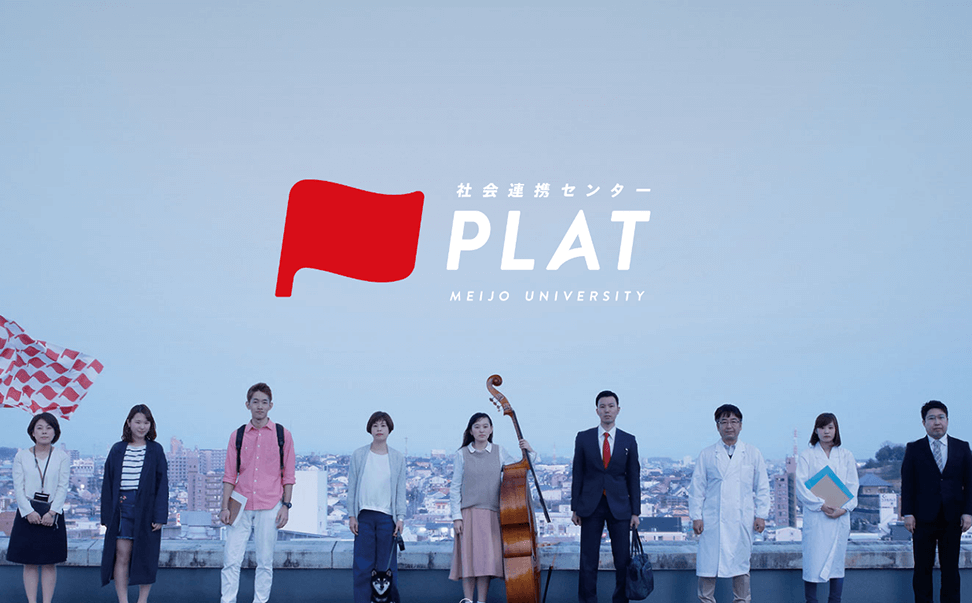トップページ/ニュース 薬学部が第23回「高校生体験実験講習会」を開催
-
 最近の名城大学薬学部について紹介する亀井浩行学部長
最近の名城大学薬学部について紹介する亀井浩行学部長
-
 この実験の目的や概略を説明する吉田准教授
この実験の目的や概略を説明する吉田准教授
2025年7月26日(土)、本学八事キャンパス薬学部で高校生を対象に「高校生体験実験講習会」が開催されました。
同講習会は実験の楽しさや薬学の魅力を伝えるために2000年度からはじまり、今回で23回目の開催でした。今回のテーマは「湿布薬の成分から解熱鎮痛薬を化学合成してみよう」。今回も定員32名を大幅に超える120名の応募があり、厳正な抽選の結果当選した31名(当日3名欠席)と高校教諭1名が参加しました。猛暑の中、来校した参加者は13時から17時までの4時間、解熱鎮痛薬の合成に取り組みました。薬化学研究室の吉田圭佑准教授が、医薬品を創り出す化学の魅力について紹介し、医薬品がどのような工程を経てつくられているのか、など解説しました。
有効成分を飲みやすくして効能を発揮できるように、薬ができあがるまでの過程を体験
参加者は8つのグループに分かれて北垣伸治教授や学生スタッフからも器具や操作方法の説明を受けました。1つ目の実験では、湿布薬の成分(サリチル酸メチル)から解熱鎮痛薬(サリチルアミド)を合成し、その重量を確認し、各グループで収率を比較しました。2つ目の実験では、合成したサリチルアミドからさらに同様に良く使用されている解熱鎮痛薬エテンザミドを合成しました。そして最後に、TLC板にUVランプを当て、合成した化合物が標準品(標品)と同じ高さまで展開されたかを確認しました。
一段落ついたところでグループごとに研究室を移動し休憩。参加者は学生スタッフから、大学受験や現在の大学生活について興味深く聞いていました。
受講後のアンケートでは、実際に大学の実習室で直接先生方から指導を受けて実験できとてもよかった、同じ方法で実験をしても全く同じ結果になるとは限らないないことを知れた、薬学部でどのようなことを学習しているか感じることができ進路選択に役立ったといった意見がみられ、非常に好評でした。
次回は令和7年11月29日(土)午後に「蛍光色素フルオレセインを合成してみよう」と題して予定しています。詳しくは10月以降に大学ウェブサイトをご確認ください。
-
 北垣教授から直接指導を受ける参加者たち
北垣教授から直接指導を受ける参加者たち
-
 操作方法を優しく説明する名城生
操作方法を優しく説明する名城生
-
 最後に参加者全員で
最後に参加者全員で