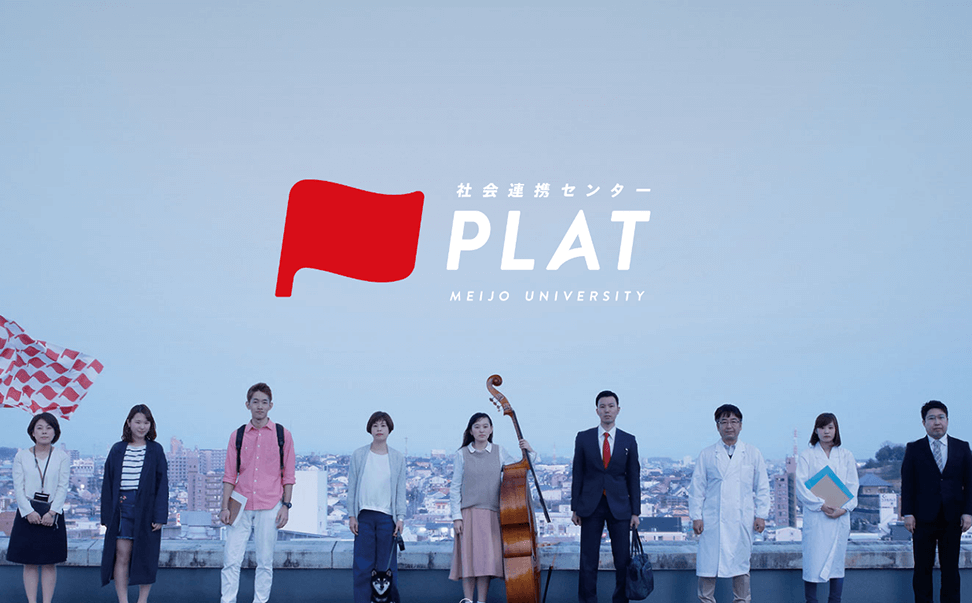トップページ/ニュース 障害者差別解消法研修会を開催〜教職員60名が障がい学生支援について学ぶ〜
障害者差別解消法と大学における障がい学生支援の理解を深める
-
 天白C共通講義棟東 E102で開催された研修会
天白C共通講義棟東 E102で開催された研修会
-
 冒頭に挨拶する理工学部村瀬勇介教授
冒頭に挨拶する理工学部村瀬勇介教授
2025年9月10日(水)、天白キャンパス共通講義棟東E102教室にて障がい学生支援センター主催の研修会を開催し、60名の教職員が参加しました。
今回の研修会では、放送大学教授の川島聡氏を講師に迎え、「障害学生支援と障害者差別解消法」をテーマに講演と質疑応答の2部構成で実施されました。障害者差別解消法は「障害による差別を解消し、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現すること」を目的として2016年4月に施行された法律です。
この法律により、国公立・私立を問わず、すべての大学で障がいのある学生に対する不当な差別的取り扱いが禁止されてきました。さらに、2024年4月の改正法施行により、すべての大学において合理的配慮の提供が義務化されるという重要な転換点を迎えています。この義務化に対応するため、高等教育機関では障がい学生支援の体制整備が急務となっています。
法律が示す「差別」と「障がい」の正しい理解の重要性
川島氏は講演の中で「多くの人は、差別をしないことが大事だと漠然と考えがちだが、その感覚はひとそれぞれで、だれもが良かれと思って行動している。最低限、法律が示す差別とは何かを知ることが大事」と強調しました。
研修会では、障害者差別解消法の基礎知識として、法律の目的や対象範囲、禁止される差別の定義などが解説されました。また、法律が求める合理的配慮の具体例や実践方法についても詳細に説明され、参加した教職員は熱心にメモを取りながら聴講していました。
合理的配慮とは、障がいのある人が他の人と平等に権利を享受するために必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、その提供には個々の状況に応じた対応が求められます。大学においては、授業や試験での配慮、施設・設備のアクセシビリティ向上、情報保障などが例として挙げられます。
質疑応答の時間では、参加者から「具体的にどのような対応が合理的配慮に当たるのか、本質を相手にわかりやすく伝えるためにはどうすればよいか」「学内における合理的配慮の範囲、学内ルール整備の注意点」「実習先での合理的配慮の提供について」など、実務に直結する質問が多く寄せられました。川島氏は一つひとつの質問に対して、法的観点と実践的な視点を交えながら丁寧に回答し、参加者の理解を深めました。
-
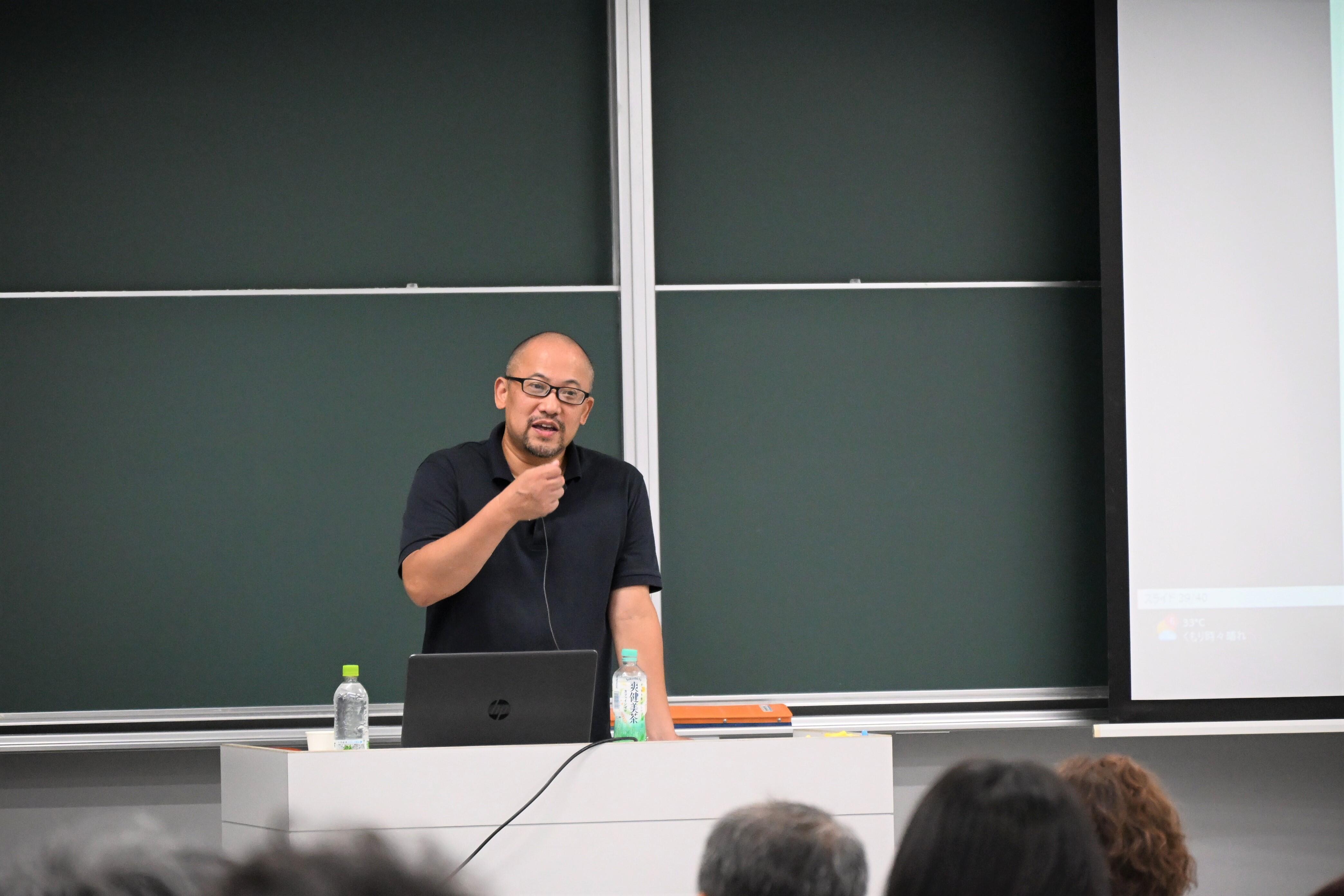 放送大学の川島聡教授
放送大学の川島聡教授
-
 質疑応答の様子
質疑応答の様子