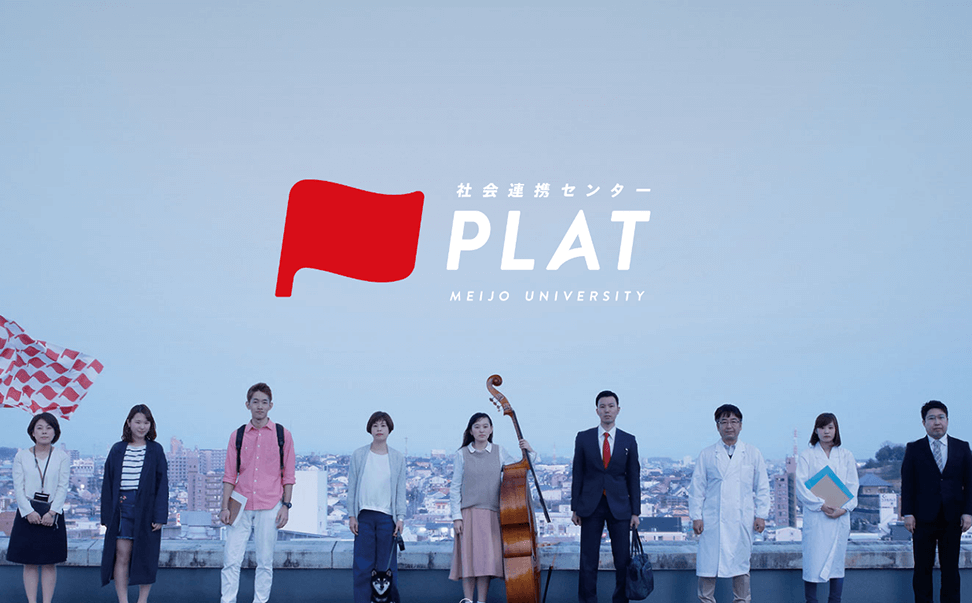トップページ/ニュース アーナンダ・クマーラ名誉教授が人間学部で2、3年生を対象に特別講義
テーマは「スリランカにおける国際協力と開発教育の実践を通じて」
 講演するクマーラ名誉教授
講演するクマーラ名誉教授
本学外国語学部の初代学部長を務めたアーナンダ・クマーラ名誉教授が10月17日、ナゴヤドーム前キャンパスで人間学部の2、3年生を対象に「スリランカにおける国際協力と開発教育の実践を通じて」と題して特別講演を行いました。受講した約160人の学生やNGOの理事、ボランティアリーダー、樹木医らを前に、クマーラ名誉教授は自らが理事長を務める国際支援NGOの活動内容や国際協力支援を行う際に欠かせない視点などを解説しました。
開発支援では「相手の『誇り』を傷つけない形での活動が大切」と指摘
-
 特別講義の様子
特別講義の様子
クマーラ名誉教授は現在、スリランカ初の日系の大学である「LNBTI(Lanka Nippon BizTech Institute)」の学長を務めているほか、グローバル人材育成教育学会の会長、日本の国際支援NGO「タランガ・フレンドシップ・グループ」(TFG)の理事長も担っており、2023年には外務大臣賞を受賞しています。
講演でクマーラ名誉教授はまず、スリランカの概要を紹介したうえで、スリランカでのTFGの活動を草の根の国際協力団体として行ってきた背景や、ボランティア活動の具体的な内容を説明。TFGは貧困という側面だけに焦点を当てて支援するのではなく、一般教育レベルが途上国の中では比較的高い特徴を生かし、インフラ開発が遅れて最も貧しいと言われる「低開発村」を中心とした職業訓練や専門教育の支援を紹介しました。
「国際支援の現場に足を運んだ大学生が多くの学びを得ている」とも強調
クマーラ名誉教授はこうした活動に関して、貧困や支援されることに伴う心理的な側面についても考慮に入れることが重要と指摘。「誇り」「自尊感情」「自己肯定感」「自信」はどのような状況であっても大切となるが、とりわけ開発支援を行う際には「貧困や辛い状況から脱却するために大切な要素」と強調。「相手の『誇り』を傷つけない形での活動が大切」と学生たちにメッセージを送りました。
「国際協力活動は支援を受ける国の人々が受益者だと考えられているが、国際支援の現場に足を運んだ大学生が多くの学びを得ている」とも訴えたクマーラ名誉教授。受講した学生からは「人としての『誇り』を傷つけずポジティブに生きていくための支援も重要で、精神的な豊かさや幸福度を高めるために私たちにできることを考えるという視点も持つべきだと知ることができた」「貧困という問題はとても深刻なものだと考えていたが、意外とその糸口は身近にあるのだと感じた」などといった感想が寄せられました。