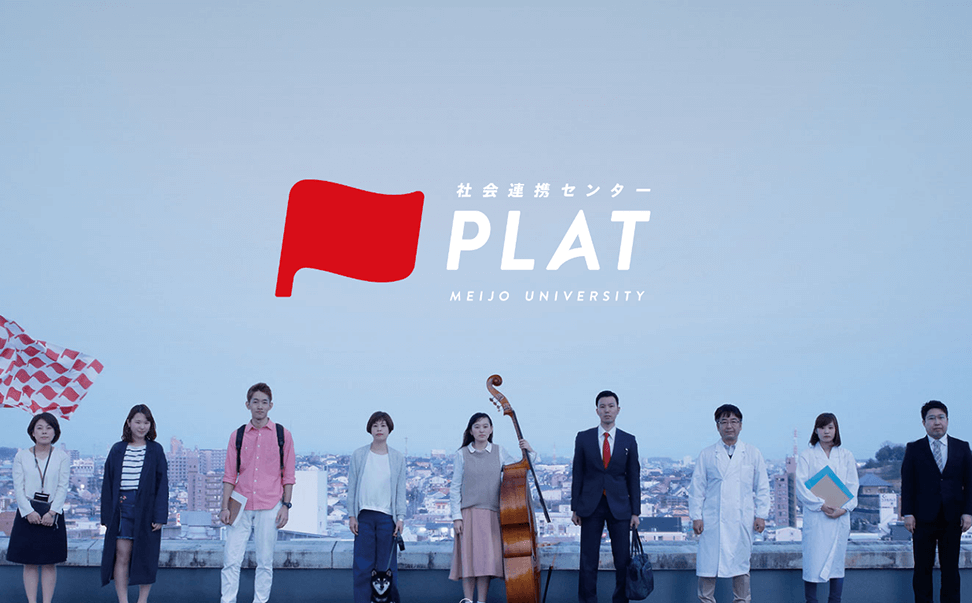トップページ/ニュース 総合研究所30周年記念シンポジウムを開催
テーマは「学際的アプローチによる社会課題解決への挑戦」
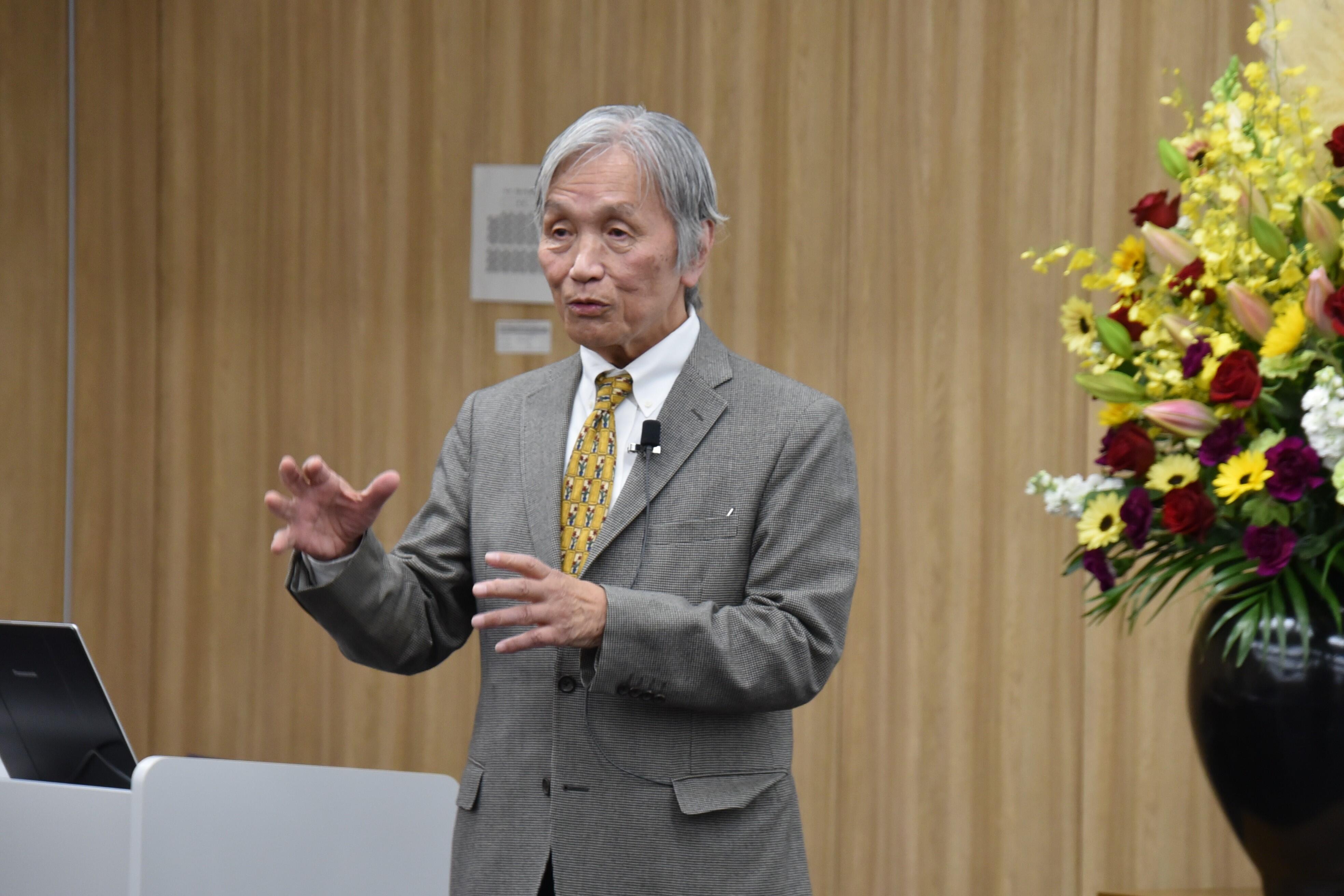 基調講演後に質問に答える佐川特任教授
基調講演後に質問に答える佐川特任教授
「名城大学総合研究所」(所長・小髙猛司理工学部教授)の設立30周年を記念したシンポジウム「学際的アプローチによる社会課題解決への挑戦」が10月30日、天白キャンパス研究実験棟Ⅳで開催されました。教員や学生ら約120人が聴講し、佐川眞人特任教授による基調講演やパネルディスカッションを通して、これまでの総合研究所の成果や社会課題の解決に向けた今後の本学の研究の在り方などについて理解を深めました。
本学総合研究所は1994年、学部学科の壁を越えた横断的な学際的研究や産官学の連携による共同研究を推進し、本学の学術文化の発展に寄与する目的で設立されました。以来、学術研究奨励助成制度の整備や30以上に及ぶ研究センターの創設、カーボンニュートラル推進機構の設置などに取り組み、その研究成果を社会に還元してきました。
佐川眞人特任教授が基調講演 教員や学生ら約120人が聴講
-
 あいさつする野口学長
あいさつする野口学長
-
 講演する佐川特任教授
講演する佐川特任教授
記念シンポジウムでは、初めに野口光宣学長が「総合研究所の30年間を振り返るとともに、今後の本学の研究の在り方や社会課題との関わりについて、あらためて考える機会にしていただきたい」とあいさつ。続いて、カーボンニュートラル推進機構のシニアフェローも務める佐川特任教授が登壇し「Nd(ネオジム)磁石の発明 若手研究者はイノベーションを起こし、年配研究者は究極を目指す」と題して基調講演を行いました。
この中で佐川特任教授は、「今のニーズではなく、10年後のニーズに基づく研究を」と提案したうえで、「誰も研究しておらず、この時のニーズではなかった」という希土類磁石が10年後のニーズと考え、管理職ポストも捨てて転職してネオジム磁石の開発につなげた自らの研究の歩みを紹介。「ネオジム磁石は今や、エアコンやモーター、EVなどに活用されて大活躍している」と力を込めました。
年配研究者に向けて「82歳になる今も完璧な産業用磁石を目指して研究している」と強調し、若手研究者には「イノベーションを起こすことを目指してほしい」と述べ、そのために「若い人が非公式の研究をする時間を与えてほしい」と訴えました。聴講者からの「失敗すると前へ進めない。どうしたらいいか?」との質問には「失敗しても次のアイデアを出せばいい。私は歩いている時など時間があったら考えている」と答えていました。
佐川特任教授と3研究センター長によるパネルディスカッションも
パネルディスカッションは小髙所長がコーディネーターを務め、佐川特任教授に加え、光デバイス研究センター長の竹内哲也理工学部教授とメディカルAI研究センター長の寺本篤司情報工学部教授、サイケデリック薬物療法による革新的うつ病治療センター長の衣斐大祐薬学部准教授がパネリストとなり、初めに小髙教授が総合研究所の歩みや概要、各センター長がそれぞれの研究センターの研究目的や成果と課題などを説明しました。
続くディスカッションでは、「10年後を想定した研究テーマは?」との問いに、「無限に応用できる光を使ってエネルギー問題を解決」「AIを活用した医療の効率化」などが挙げられ、これから総合研究所に望むことには「10年後を想定した研究テーマに対応できる助成制度の創設」が挙げられたほか、「若手人材を育成するため、大学全体として博士課程に進む学生をサポートする体制をさらに充実させてほしい」との意見で3センター長が一致。佐川特任教授も「博士課程がいちばん大切。ぜひ進んでほしい」と訴えました。
-
 竹内センター長
竹内センター長
-
 寺本センター長
寺本センター長
-
 衣斐センター長
衣斐センター長
-
 3センター長
3センター長
-
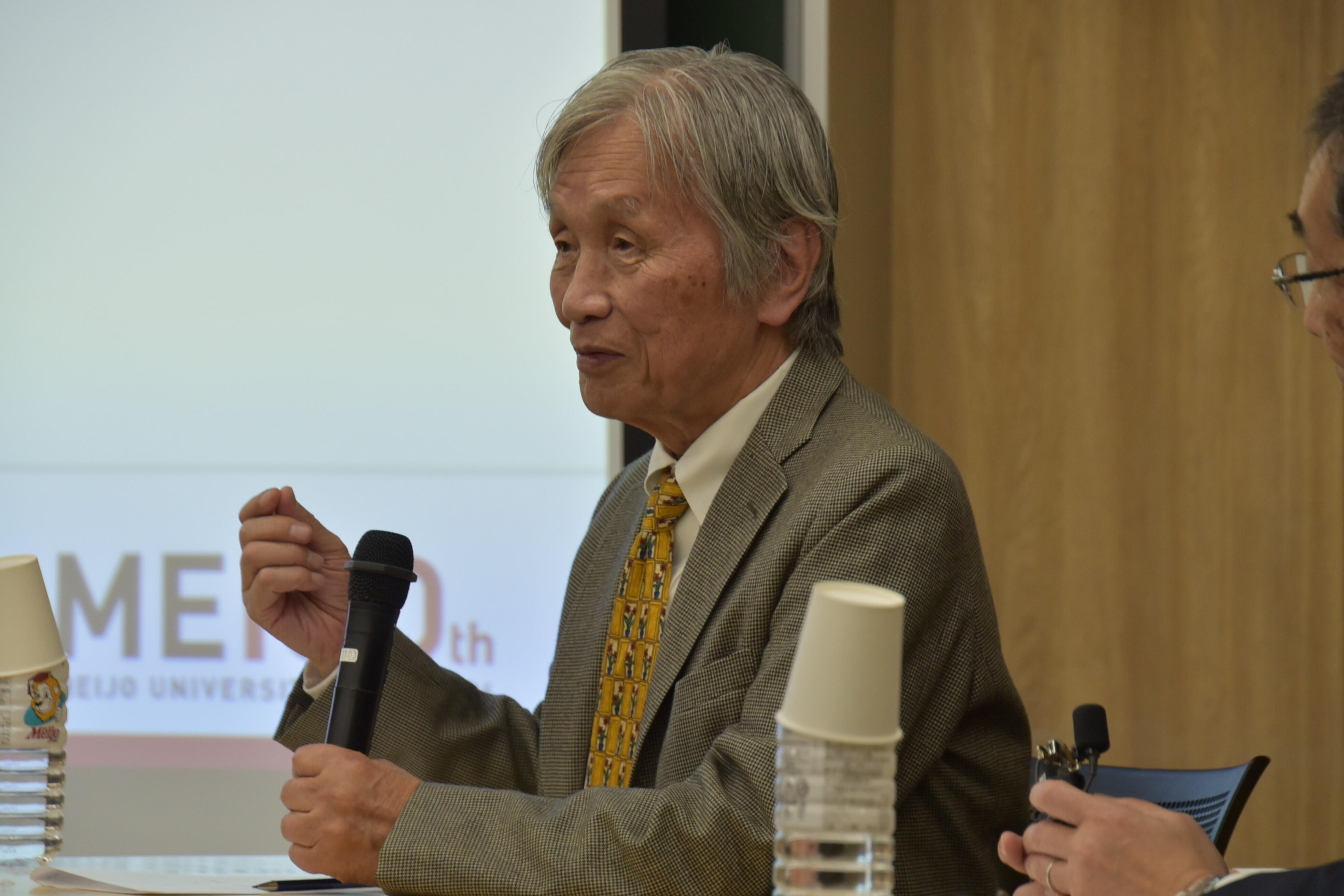 佐川特任教授
佐川特任教授
-
 コーディネーターを務める小髙所長
コーディネーターを務める小髙所長