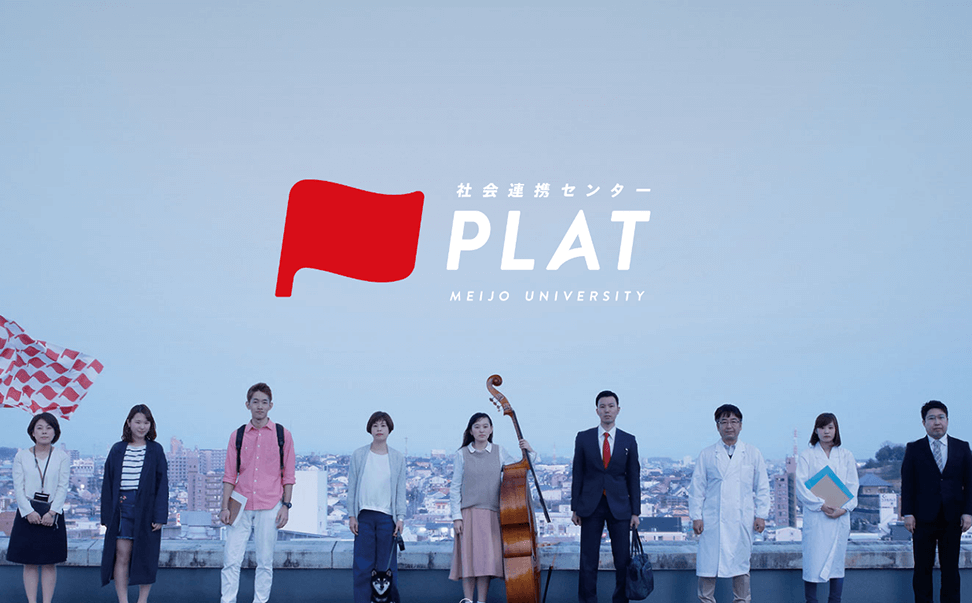トップページ/ニュース 経営学部山岡ゼミにて山並憲司氏を招いた特別講演会を開催
-
 株式会社Smart Opinion 代表取締役社長 山並 憲司氏
株式会社Smart Opinion 代表取締役社長 山並 憲司氏
経営学部山岡隆志ゼミナールでは、11月13日(木)、Smart Opinion代表の山並憲司氏をお招きし、特別講演会「日米での起業と事業化―社会課題解決型スタートアップの創り方」を開催しました。
講演に先立ち、山岡教授より山並氏の多岐にわたるキャリアが紹介され、「学生の皆さんの将来の参考になるお話をぜひ聞いてください」と挨拶がありました。
■ 山並憲司氏プロフィール
東京大学大学院、M.I.T.スローン経営大学院、Duke Law School卒業。大学院時代に医療画像×AIを研究後、経済産業省に入省し個人情報保護制度の創設に携わる。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニー、楽天の執行役員などを経て、多くの新規事業を立ち上げる。母親の乳がん経験をきっかけに、「乳がんによって幸せが奪われることが一人でも少なくなる世界を実現する」ことを目指し、AIを活用した乳がん検診を推進するSmart Opinion株式会社を創業。
社会課題解決に挑む―ゼロから医療分野の事業化に成功
講演の冒頭で山並氏は、これまで歩んできた多彩なキャリアと、アメリカでの実業および起業経験について紹介しました。楽天には一般職として入社し、その後マネージャー、部長、役員へと短期間で昇格しました。さらに、楽天が買収した米国の電子商取引サイトへナンバー2として派遣され、周囲が全員米国人であり、かつ買収された側の社員という厳しい環境の中で大きな苦労を経験したと振り返りました。渡米後は、インターネット事業と組織運営で培った経験を生かし、米国で起業にも挑戦しました。ユーザー視点を重視したオンラインショールームを立ち上げましたが、流入数の確保が難しく閉鎖を余儀なくされた経験も率直に語り、「挑戦することそのものに価値があり、失敗からこそ多くを学べる」と強調しました。
現在、山並氏が代表を務める株式会社スマートオピニオンは、慶應義塾大学医学部と共同で、乳がんを対象とした超音波画像の人工知能診断支援ソフト「スマートオピニオン METIS Eye」を開発しています。本製品は昨年、国から薬事承認を取得し、2025年8月19日の販売開始が発表され、発表後は複数のテレビ局のニュースで取り上げられ大きな注目を集めました。
製品化に至るまでには、医療現場が求める高い精度を実現するため、多大な時間と労力が必要でした。5,000例を超える乳がん画像を人工知能に学習させ、病変を確実に認識できるレベルまで精度を引き上げる必要がありました。また、医療機器の開発には医療機関との連携や厚生労働省の認可手続きなど、高い参入障壁があります。共同開発者である慶應義塾大学医学部教授の林田哲医師は山並氏の高校時代の同級生であり、山並氏自身が経済産業省出身であることから、人脈を生かした官庁対応が大きな後押しになったと語られました。ゼロからの参入を実現できた背景には、深い人との関係性と専門性に基づく強固な協力体制がありました。現在は、米国のMayo Clinicとの共同研究も進めており、山並氏は「女性の健康への取り組みが企業価値に直結する時代。戦略的な福利厚生として人工知能乳がん検診を導入することで、働く女性の生産性向上に寄与できる」と展望を述べました。
社会で評価されるための「正しい差別化」を理解する
社会で評価されるためには、自身の強みを明確にし、他者との差別化を適切に示すことが不可欠です。試験のように客観的な評価基準が明確な場面とは異なり、実社会における評価はしばしば主観的な印象に基づいて行われます。そのため、残念ながら、十分な能力を発揮できていない人や大きな成果を上げられていない人ほど、他者との差を埋めようとして他者の評価を下げる行動に出ることがあります。たとえば、根拠のない悪口を広めたり、些細なミスを過度に強調して評価を低く見せようとする行動は、その典型です。皆さんには、決してそのような行動を取らない姿勢を大切にしてほしいと思います。
こうした行為は、最終的には自らの信頼を損ね、成果や機会を遠ざける要因となります。しかし、評価を下げられる側にとっては、短期的に不利益を被る可能性がある点にも注意が必要です。突出した成果を上げる人材がこのような状況に直面することは、ある意味では避けがたい側面もありますが、それでも誠実で質の高い人材が集まる組織に身を置くことは、健全なキャリア形成にとって非常に重要です。組織文化やメンバーの姿勢を見極める視点は、企業選びを行う際にも大切な判断基準となるでしょう。
複数の専門性を身につけ差別化された人材に
山並氏は学生に向けて、「自分に限界を設けず、複合的に価値を創造できる人になってほしい」と語りました。社会で求められる人材とは、「自分にしかない差別化の要素」を備えた存在であると強調します。山並氏自身は、大学院で電子工学を専攻し、経済産業省で国家プロジェクトに携わり、海外で経営学と法学を修め、戦略コンサルティングで企業戦略の知見を深め、楽天でデジタル事業の専門性を磨きました。さらに、海外での事業運営や米国での起業など、多岐にわたる経験を積み重ねてきました。「一つや二つの経験であれば同様の経歴を持つ人はいる。しかし、これだけ複数の専門性が掛け合わさった人材はほとんどいない」と語り、複数の専門性を統合することが差別化の鍵であると説きました。
また、夢や目標を持つことの重要性にも触れ、自身は「20代は社会への貢献、30代は経済への貢献、40代は社会への提案」というように、10年単位で人生を設計してきたと紹介しました。将来像を明確に描いたうえで、40代・50代でどのような姿を目指すのかを逆算し、新卒時の企業選びに反映させることは、極めて有効なキャリア戦略であると助言しました。さらに、「技術や専門性を持たないまま起業しても、社会的意義の薄い事業に陥る可能性がある」と指摘し、たとえ将来的に起業を志していたとしても、まずは大企業で経験を積み、専門性を高めることが重要であると述べました。そのうえで、初めて取り組む価値のあるテーマに挑戦できると強調しました。安易に誰でもできる起業に走るのではなく、社会的意義を伴う事業を創出するための土台として専門性を磨くことの大切さを学生に説きます。
質疑応答では、学生からの質問に丁寧に答えながら、「心からわくわくできる対象を持つことが大切である」「課題の解決を目的とした起業は社会の根本的な変革を目指すものである」といった、実体験に基づく力強いメッセージを送りました。最後に、「自分が存在して良かったと他者に思ってもらえる生き方をしたい」と語り、講演は大きな拍手に包まれて締めくくられました。