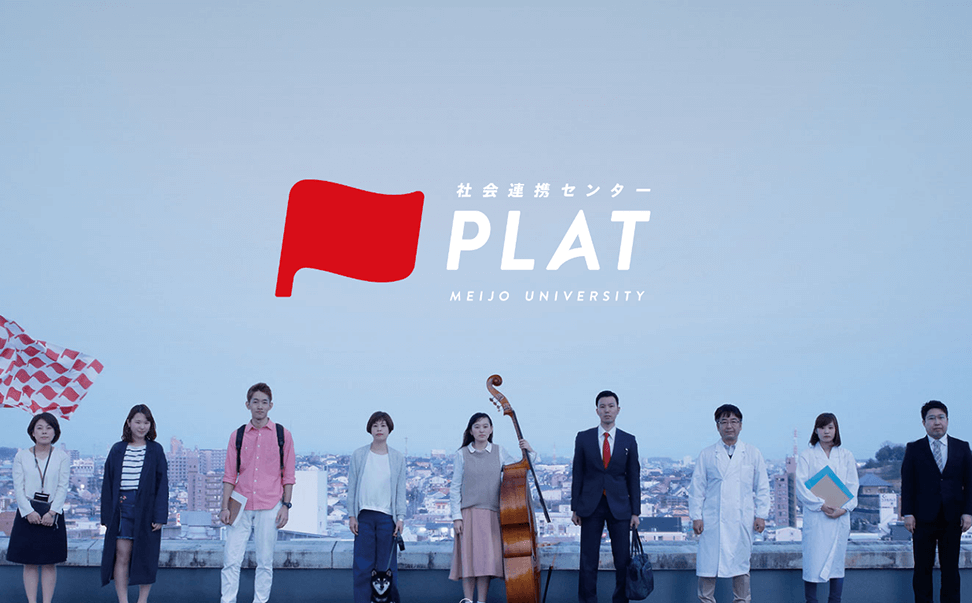特設サイト第33回 漢方処方解説(11)半夏瀉心湯
この冬一番の寒さという日々が続いています。
夕食に毎晩鍋もの、というご家庭も多いはず…。
さて、今回取り上げる漢方処方は半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)です。
これはこの連載でもおなじみの「傷寒論(しょうかんろん)」に出てくる処方で、柴胡剤(さいこざい)の代表格である小柴胡湯(しょうさいことう)と構成生薬もよく似ており、また使われる時期も「少陽病期(しょうようびょうき)」と同じという処方です。構成生薬は、黄連(おうれん)、黄芩(おうごん)、半夏(はんげ)、乾姜(かんきょう)、人参(にんじん)、甘草(かんぞう)、大棗(たいそう)の7種です。小柴胡湯が「柴胡」と「黄芩」を中心とした処方ということで「柴胡剤」と呼ばれるように、半夏瀉心湯は「黄連」と「黄芩」を中心とした「芩連剤(ごんれんざい)」と呼ばれます。つまり、「黄芩」と何を組み合わせるかで、異なる薬方になるという興味深い例です。
現代医学において、半夏瀉心湯は急・慢性胃腸カタル、発酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔い、げっぷ、胸やけなどに応用されています。漢方医学的には、「心下痞硬(しんかひこう)」と呼ばれる、みぞおちの違和感やつかえがあるような自覚症状を本処方の選択時の決め手とします。この処方も「瀉心湯」類と呼ばれるように、よく似た仲間(類方といいます)を持ち、それぞれ使い方がありますが、そのお話はまた別の機会に。
古典によれば、本処方はまだ熱のある時期に間違って下剤を使ったことで、腸が冷えて下痢になったものの、まだ胃に熱があるため、その境目であるみぞおちがつかえて硬くなった場合に用いるとされています。そのため、胃の熱を冷ますのに「黄連」と「黄芩」を使い、腸を温めるのに「生姜」ではなく「乾姜」を使います。
なかなか理にかなっていますよね?
最近では、抗がん剤の副作用として出現する口内炎の治療に使われることもありますが、元々の適応症にも口内炎は書かれています。冒頭の鍋物の話ではないですが、食事中つい唇の内側を噛んでしまって口内炎にしてしまい、先日もお世話になりました。でも、なぜかこの一年口内炎ができることが多く、ビタミン不足なのかと少々悩んでいます。
この処方もドラッグストアに並んでいますから、気がついたときに手にとって見て下さい。
(2017.1.26)