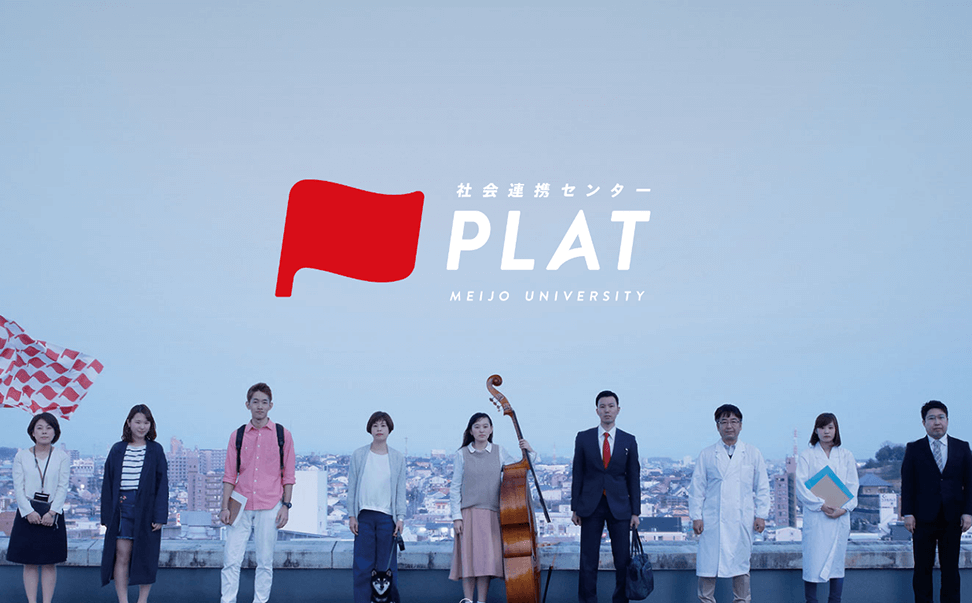特設サイト第2部 第1回 駒方の春風
新制大学の始動
商学部のみの新制大学として1949年4月に発足した名城大学。授業は本部や附属高校のあった名古屋市中村区の中村校舎で行われました。1期生として入学した名古屋市千種区の水野貢さん(82)は入学式で、新入生代表としてあいさつしました。
「入学式当日、大学に行ったら、歩み寄ってきた先生にいきなり頼まれました。旧制中学時代にも経験があったことなので引き受けました。田中壽一学長の前で、学生として、名城大学の名前を辱めないよう勉学に励みますというようなことを言いました」と水野さんは語ります。
戦時下、陸軍は東京の立川に航空機工場を集約するため1940年に立川航空工廠を設立しました。名古屋陸軍造兵廠千種兵器製造所で航空機製造に従事していた従業員の大半が立川への転勤を余儀なくされました。水野さんの父親も小学4年生だった水野さんら家族とともに立川に引っ越しました。中学校は都立立川高校の前身である旧制府立二中に入学。新制の立川高校第1回卒業生となり名古屋に戻り、発足したばかりの名城大学1期生として入学しました。
商学部創立30周年記念誌『碑』(いしぶみ)(1978年9月23日発行)に、当時の柴山昇教授(1893~1981)は「商学部誕生30年の歩みを見守って」という一文を寄せています。「東枇杷島駅から新富町に渡って、国鉄東海道線のトンネルをくぐって歩くこと数十歩にして右に切れて、左側に2階建て木造の校舎がある。それが商学部の校舎で、東側の長い廊下の南の端に木造新築の校舎があった。ここが商学部発祥の地ともいうことができる」と書いています。さらに柴山教授は、昼間部の授業を終えた、夜間部授業が始まるまでの時間帯を、「窓から、庄内川の堤防を行き来する人馬を眺めておるしかなく、そのうちに廊下が騒がしくなって、人声が聞こえ始めると夜の授業の始まりのベルが鳴り出すのである」と記しています。
駒方キャンパス
名城大学は2期生を迎えた1950年度からは昭和区の駒方校舎に移り、商学部は法商学部商学科として新たなスタートを切りました。柴山教授は『碑』の中で、駒方校舎についても、「門を入ると、左側に大講堂があり、正面に5棟の校舎が縦に並んで建っていた。その向って左側の棟が商学部の教室にあてられた」と書いていました。
名城大学は膨張していました。法商学部には法学科も開設されたほか、中村校舎には理工学部が誕生。農学部も開設されました。ただ、キャンパスとなるはずの春日井市の旧名古屋陸軍造兵廠鷹来製造所跡地の整備が整うまでの1年間は中村校舎で授業が行われました。短期大学部も発足し、駒方校舎で本格的な授業を開始したほか、1947年に開校した旧制名古屋専門学校も1955年度閉校までは、法科、商科の授業が駒方校舎で行われました。
殺風景だった駒方校舎が学生たちであふれました。しかし、陸軍造兵廠の少年工員たちのための駒方寮であった施設を、十分な手入れをすることもなく転用していたこともあり、教室のいたみはひどく、畳敷の部屋を板敷に改造した教室はきしみ、2階を歩くと抜け落ちるのでは心配される廊下もあるほどでした。
「使っていない校舎の中には、まるで怪獣の博物館のような骨組みだけの校舎もあった」。水野さんと同期の法商学部1期生、山田昭治さん(83)(名古屋市中区大須)は、中村校舎から移った当時の駒方校舎の様子を振り返ります。
愛知国体めざした運動部
駒方キャンパスでは校舎や講堂、雑草に覆われたグランドのあちこちで、運動部の活動が始まっていました。1950年は、第5回国民体育大会が愛知県で開催された年でもありました。街ではスポーツによる復興を目指す動きが加速し、名古屋市では中心道路が100m以上に広がり、5万人収容の瑞穂競技場や、金山体育館など19施設が新設されました。
大学運動部には国体での活躍に熱い期待が集まっていました。山田さんによると、名城大学でも野球部を始め、陸上、柔道、空手、重量挙げ、水泳、庭球、卓球、バドミントン、山岳スキー、フェンシング、レスリング、サッカー、ラグビーなどの部が動き出していました。「国体では参加すれば参加点がつく。名古屋では男子学生が多い名城大学と愛知大学への期待が特に大きかった。名城でも急ごしらえの部が相次ぎ、私も剣道経験者ということでフェンシング部の創立に駆り出されました」と山田さんは振り返ります。
1950年9月19日付の毎日信新聞に、「待ち遠しい国体 張り切る名城大フェンシング・チーム」という記事が掲載されました。
千切れ雲が二つ三つ飛び立って、純白のユニフォームに身を固めた若人たちの右手から気合鋭くエイッ、ターッと繰り出されるエッペ(剣)。秋草を踏むステップにいつしか背に汗がにじむ。
これは東海地方では珍しい学生フェンシングの野外練習で、21日から名古屋を中心に開かれる国体予選に備えて、仕上げに余念のない名城大フェンシング部である。元法政ナンバー・ワンの山田六郎氏(名古屋田口百貨店勤務)を正式コーチに迎えた昨年10月、練習をはじめたばかりで、用具も東京まで買いに行く有様というが、わずかの間にめっきり上達。今年の夏休みは知多半島大野で合宿練習を行い、専ら足のトレーニングに知多海岸を十数キロ朝晩走った甲斐もあり耐久力に十分の自信を持ったそうだ。国体フェンシングに郷土愛知を代表して初出場の選手の頭上に栄あれ。
フェンシング部の練習場となったのは駒方キャンパスの中庭。山田さんは、「指導してくれた山田さんも仕事があり、いつも来てくれるわけではなかった。フェンシング協会から配られた冊子を見ながら、みんな勝手に学ぶこともあった。そのうちに珍しさもあって新聞社が取材に来ました」と振り返ります。
躍動する学生たち
続々と誕生する運動部。しかし、活動の拠点や練習場は自分たちで生み出すしかありませんでした。陸上競技と言ってもトラックはなく、やり投げ円盤投げなどフィールド競技が中心となりました。山田さんがフェンシング部に加わったのは、好きな剣道がマッカーサー命令で一時禁止されていたこともありました。正式な籍はありませんでしたが、空手部にも入っていました。
山田さんの自宅に近い、名古屋市中区の白川公園一帯にはアメリカ村と呼ばれた駐留米軍居住区がありました。山田さんは、そこで通訳のアルバイトをしていた名城大学生を通じて米兵たちから、アメリカンフットボールの対戦チームの結成を頼まれました。ルールもよく分からず、道具もありません。「ラグビー、ボクシング、サッカーをやっている屈強な学生たちを集めて来てほしい。大体はラグビーに似ているが、後退しながらやる。対戦してくれたらビフテキをつけるから」。アメフトの試合に飢えていた米兵たちは陽気で大らかでした。試合は、当時は日本人が立ち入り禁止だった鶴舞公園で行われました。「体当たりでぶつかりましたが、全く歯が立ちませんでした。グラウンドのそばには救急車2台が待機したのを覚えています」と山田さんは苦笑します。
文化系クラブも続々生まれていました。水野さんは文芸部とグリークラブに所属しました。山田さんは駒方校舎に移った1950年5月に「名城大学新聞」の創刊号を出した新聞会にも参加しました。担当したのは広告集め。新聞が言論の自由を貫くには、学生団体とはいえ、経済的に独立していかなければならないという考えからでした。
ジャズ、ダンス部も人気でした。大学に入り直してきた年輩者も多く、ジャズの魅力を教えてくれる学生もおり、アメリカで流行っているジャズがあっという間に広まりました。笠置シズ子のブギウギや、美空ひばりの「ひばりの花売娘」のレコードが飛ぶように売れていた時代。ルンバ、タンゴ、クイックとダンスも盛んになり、名城大学からも土曜日、日曜日には柳橋で開かれるダンスパーティーに繰り出す学生たちが相次ぎました。
女子学生第1号は主婦学生
水野さんの卒業アルバムには、駒方校舎時代の興味深い写真が何枚も収録されていました。名古屋専門学校に1948年に入学した女子学生第1号の岸田陽子さん(津市)の写真もありました。ちなみに岸田さんの名前は、「名城大学新聞』創刊号(1950年7月1日)の「学生会全役員決定」の記事の中にも「庶務」ポストとして紹介されていました。
新制大学第1号と思われる女子学生の写真もありました。コーラス部員(グリークラブ)で水野さんとともに写っている岸本三和子さんです。岸本さんについても「名城大学新聞」第5号(1951年2月3日)が、「教授夫人の受験 商学科3年へ編入」と紹介していました。「さる27、28日に行われた第1次入試に南山大学講師岸本氏夫人三和子さん(22)は商科3年の編入試験に合格した。夫人は神戸経済大付属経営学専門部卒」。
山田さんは「クラスには55人か56の同級生がいましたが、紅一点が岸本さん。南山大学の教員住宅から歩いて通っていました。家庭を持っているせいか忙しかったのでしょう、試験でも開始時間ぎりぎり駆け込んできていました。経営学の知識は豊富で、よくアドバイスしてもらいました」と振り返ります。
工夫の精紳
名城大学で開学と同時に一斉に始動したクラブ活動について、空手部の顧問もつとめた柴山教授は駒方学生会学術局発行の「学術研究」第1号(1965年11月)にも「学風と文化」のテーマで寄稿し、「大学の精紳がクラブ活動の中に息づいていた」と書いています。
「最初にできたクラブが野球、空手、陸上、柔道、剣道、レスリング部などで、クラブ活動としてはずいぶん不自由な環境において始まったものである。道具もそろっておらず、走り回るグラウンド、道具といったものも手狭どころの騒ぎではなく、全然ないも同然で、そこでクラブ員が工夫してどうにかこうにかやっていた。この『工夫』ということがクラブ活動一般の持つ精神であり、同時にまた大学自治の精紳、つまりは大学の学風ということにつらなるものである」と書いています。
3期生の回想
法商学部商学科3期生として1951年4月に入学した桂川澈三(てつぞう)さん(故人)が、柴山教授の文章が掲載された『碑』に「草創の門」という題で、駒方校舎時代を回顧した一文を寄せています。
<草創の門>
昭和26年4月も半ば、ぼくは法商学部商学科第3回生として、駒方の門をくぐった。幾棟かが立ち並ぶモルタル2階建ての旧兵舎が校舎であり、これといった変化もない風情は、今一つ何かが要求されるようだった。空間をそーっと駆け抜けるそよ風の調べに舞踊する雑草の辺りは、正に雑ぱくたるものがあった。校庭正面、奥深いところに事務局があり、その事務局玄関をはさむ両脇に、雨ざらしとなっているのであろう、色あせたスクールバス2台がこっちを向いていた。ラジエータ部分を眺める限り、祭事の獅子頭か、神社の狛犬を思せるような格好に、先ずは奇妙さを覚えた。
およそ150名がA・Bの2組に別れ、キャンパス南側角にあたり、東西に伸びた校舎2室に座したのがぼくら新入生の仲間であった。低い天井を支えるような構えで、直径10センチ程の鉄柱2・3本が室の中ほどに並んでいた。土足で歩く木板の床廊下は、想像以上のものがあった。室内補修工事のためか、塗りたてのペンキの臭いが漂い、強烈に鼻をつく。せめてもの入学歓迎の意味と思うほかはなかった。
母は、僕に教師の道を進めた。その大学を選んだもののどうしても納得できず、名城門下に籍を置くこととした。分岐点に立った18歳のぼくは、何か割り切れない虚しさにおおわれた。飛騨の山あいから抜け出し、「商学」を求めたことへの気持ちを整理しようと考えつつも、その自問は恥ずかしいことながら今日なお、未解決のままである。ともあれ、名城に学んだぼくの青春は、思い切り駆け回った駒方での日々であった――。
(広報専門員 中村康生)