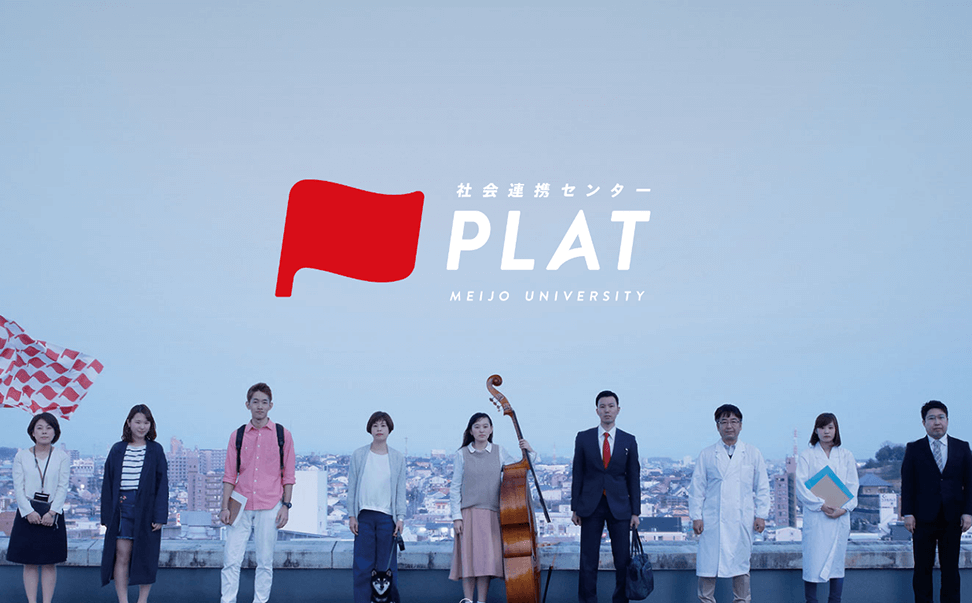特設サイト第2部 第3回 流浪の学生たち
デンマーク農業
名城大学開学2年目の1950年。法商学部、理工学部、農学部、短期大学部と総合大学への基礎固めを図った名城大学には、大学での学びを求める若者たちが続々と集まってきました。農学部1期生の稲垣一人さん(86)(愛知県小牧市)もその一人でした。
稲垣さんは、私立滝高校(江南市)の前身である滝実業学校の農業部を、太平洋戦争末期の1943年12月18日に卒業しました。本来なら1944年3月の卒業でしたが、戦局が緊迫化しての繰り上げ卒業でした。稲垣さんは志願兵として、遺書を書き残し、名古屋の歩兵第六連隊に入隊。静岡県の御前崎に近い榛原(はいばら)郡地頭方(じとうがた)村(現在の牧之原市南部)で終戦を迎えました。
舞い戻った名古屋はアメリカ軍による大空襲の猛威を見せつけるように、無残な焼野原が広がっていました。名古屋城も天守閣は燃え落ち、工場も爆撃されていました。日本が復興するには農業しかない。それもデンマークにならった近代農業でなければ。ただ、自分がそうした農業による復興の一翼を担うには、農業学校で学んだ知識は半端であり、もっと高いレベルの農業を学ばなければ。稲垣さんはそう思いました。
農学部ができる
連合国軍総司令部(GHQ)の方針で農地改革が進められていました。稲垣さんは現在の小牧市東部にあたる旧篠岡(しのおか)村の臨時職員として農地改革の仕事に従事していました。そんな矢先、春日井市にある陸軍名古屋造兵廠鷹来製作所跡地に、名城大学が農学部をつくるというニュースが飛び込んできました。1949年春、新聞が「1950年4月、名城大学農学部開校」のニュースを伝えたのを機に、稲垣さんは村役場での仕事の傍ら、さっそく受験準備を始めました。苦手な数学をはじめ、受験という難関を潜り抜けて合格できたとしても23歳での入学になります。しかし、稲垣さんには、世間ではすでに所帯を構えている同世代のことも、新制高校を卒業して入学してくる同期生たちとの年齢差とのことも気になりませんでした。自宅から通えることも経済的に負担が少なく、大きな魅力でしたし、何よりも、大学で農業を学べるというチャンスが目の前に飛び込んできたからでした。
中村校舎での授業
農学部1期生たちの授業は春日井市の鷹来校舎ではなく、理工学部のある名古屋市中村区新富町の中村校舎で始まりました。鷹来校地の整備が全くなされていなかったためです。広大な面積を誇る鷹来製作所跡地は終戦後、全くの放置状態でした。一面に身の丈にも余る笹や雑草が生い茂り、雑木や雑草の中に点在する建物も荒れ放題。鉄筋コンクリート本館(現在の農学部附属農場本館)は地下に水が貯まったままで、立ち入りが危険なほどの水深でした。
農学科の入学定員は1学年80人ですが、稲垣さんの記憶では中村校舎で一歩を踏み出した農学部1期生は40人余でした。稲垣さんら農学科の学生が9人で残りは医科・歯科進学コースの学生たちでした。当時は、医科・歯科系の大学や学部への入学を希望する学生に対し、農学部など生物系の学部で教養課程科目単位を履修して進学できる道が用意されていました。2年間の教養課程を終えた後、医学部、歯学部のある他大学への編入を目指す学生たちのための同コースは、名城大学では1950年度から1957年度まで8年間存在し、計387人を送り出しています。
農学科、医科・歯科進学コース合同での授業は理工学部と同じ校舎で行われました。ドイツ語、英語、化学などの授業が行われる教室は学生たちでいっぱいでした。
田中学長との出会い
伊藤良三さん(81)(春日井市)も1期生として農学部に入学しました。卒業後は農学部にとどまり助教授(畜産学)として定年まで母校に勤務することなる伊藤さんは、新制の私立名古屋高校を卒業したばかりの18歳で、稲垣さんより年齢では5歳後輩でした。鷹来校舎が誕生すれば、自宅から自転車で30分で通学できます。実家は農業。設備の整った大学で最新の農業を学びたい。伊藤さんもそんな期待を持って名城大学農学部の門をくぐろうとしていました。しかし、合格通知をもらって、鷹来校舎を訪れた伊藤さんは愕然としました。ぼうぼうと生い茂った笹や雑草。「本当にここに大学ができるのだろうか」。伊藤さんは不安になりました。
鷹来校舎の整備は一向に進んでいる様子はありません。中村校舎での農学科1期生たちに将来への不安が募りました。授業の合間、校舎のかたわらで、伊藤さんら数人の仲間が、不安を話し合っていました。「このままでは何の収穫もないぞ」。たばこを吸いながら語っていた同級生の1人が、小柄な男性にポンポンと背中をたたかれました。「君、君。たばこを吸うような金があったら大学に寄付しなさいよ」。男性はそう言って立ち去っていきました。「どこのおじいだ」。どこか憎めない、親しみを感じる男性は、田中壽一学長兼理事長でした。
編入試験
しかし、2年生への進級が近づくにつれ、他大学の編入試験を目指す学生たちも出てきました。京都大学農学部に入り直した学生もおり、伊藤さんも明治大学農学部の編入試験に合格しました。東京農大の編入試験に合格した仲間もいました。このままでは、農学部1期生たちの仲間は間もなくばらばらになってしまう。伊藤さんはがそんな思いでいた時、声をかけてきたのが稲垣さんでした。「どこに行っても、最後は自分でやるしかないぞ」「俺たちが頑張って、この大学の礎(いしずえ)になろう」。稲垣さんはとうとうと語りました。「さすがは社会で飯を食ってきた先輩だと思いました。稲垣さんの話を聞きながら。じゃあそうするかと、明治大学への編入を思いとどまりました」。伊藤さんはそう振り返りました。
司法試験をめざして
法学部の前身である法商学部法学科が開設されたのも農学部と同じ1950年4月。当初、授業は中村校舎で行われましたが、第一部は間もなく駒方校舎に移り、中村校舎では第二部法学科の授業が行われました。第二部法学科1期生で岐阜県のFさん(82)から、当時の思い出をつづったお手紙をいただいたのは2013年3月19日に開催された「スペシャルホームカミングデイ」の前でした。卒業して半世紀以上になる名城大学の卒業生たちのこの集いに、「欠席」の返事とともに寄せられた手紙には、岐阜県下の裁判所職員として勤務しながら、第二法商学部に通い続けたFさんの思い出の日々がつづられていました。
Fさんは新制高校を卒業して岐阜地方裁判所に就職。上司から「ずっと裁判所で働く気なら、裁判官になることを目指しなさい。それには夜学でよいから大学に入り法律をしっかり勉強して司法試験に合格することです」と声をかけてもらいました。この言葉が、開校したばかりの名城大学法商学部に入学するきっかけでした。
父親の涙
Fさんの手紙によると、当時の国家公務員の高卒初任給は3009円。税金、年金積立金、組合費などを差し引くと手取りは2000円を切る状態で、交通費は支給されませんでした。それでもFさんは親の援助は一切受けず、第二法商学部への入学を決めました。家の経済状態から、Fさんの入学に難色を示す父親。兄が、「本人が働きながらその給料で勉強したいと頼んでいるのに反対する必要はない。夜学で名古屋まで通うなんて大変だけど、卒業するまで棒を折らずに頑張れよ。多少の援助はするから。百姓は俺一人でやるから心配するな」と側面援護してくました。「兄ちゃんに迷惑をかけないよう頑張れよ」。父親が涙ぐんだ顔を悟られないよう、急いで部屋を出ていった時の情景は、半世紀を経た今も昨日のことのようにFさんの脳裏には焼き付いているそうです。
座れない教室
晴れて入学した大学の授業は、国鉄枇杷島駅近くに存在した附属高校2階一部の部屋を借り受けた教室で行われました。校門・校庭もなく、木造2階建ての、戦後に急造されたもので、キャンパスなどは存在する余地はなく、周辺は壊れかけた工場の廃屋と農地のみでした。机はどこかの廃校から取り寄せた小中学生用の、傷だらけの、古く小さく黒ずんだ代物でした。そんな状態の中で、定員40人位の教室に約80人位の法学科の生徒が熱心に講義を受けていたのです。はみ出した者の半分は教室の中、半分は廊下に、いずれも立ったままで筆記していました。教養科目以外はすべて名古屋地裁・高裁の裁判官が講師でした。
Fさんは入学した年の5月、裁判所書記官に任用され、岐阜地裁大垣支部に転勤になりました。職場から、東海道線を使っての通学時間も長くなりました。帰宅は毎日午後11時を過ぎ、何度となく終点の米原駅まで居眠りで乗り越し、翌朝、役所に直行したこともありました。在学中、司法試験に合格した同級生が現れたのはFさんらを勇気づけ、大きな誇りとなりました。ただ、残念なことにこの同期生は司法研修中に心臓の病で他界してしまいました。
3年生の時から、Fさんら第二法商学部法学科の授業は、名古屋駅に近い、名古屋市西区にあった愛知女子商業学園高校(その後校名は、愛知女子高校を経て2009年4月から啓明学館高校に改称)の校舎に移りました。校舎は地名から「菊井校舎」と呼ばれました。
鷹来校舎
農学部は、伊藤さんや稲垣さんらが2年生となった1951年4月から鷹来校舎に移りました。新しい農学科1年生たち44人も入学してきましたが、依然として整備は手つかずでした。東西南北1km以上もある広大な国管理の用地のうち、南部地区と北部地区の一部を財務局から借用し、南部地区の管理棟、病院跡を松林校舎、第二校舎として、北部地区のかつての鷹来製作所工員寮の一部が学生寮、さらにそれに付属する体育館がそのまま体育館として使われました。
稲垣さんや伊藤さんを始め、学生たちは、自分たちで買い揃えた鎌や鍬、農機具で農場や運動場の整備、開墾に取り組みました。農学部「50年の歩み」(2000年刊)の中で、同じ1期生で、三重県松阪市の中川斌(あきら)さん(84)は、鷹来校舎に移った当時の様子を「何もかも不足がちで、実験設備が足りないので、岐阜大学に出向いて授業を受けた事を思い出します」と記しています。
稲垣さんは学生会の会長として、黙々と農場整備に立ち向かいました。「名城大学農学部は、公立学校のように、施設設備を当初から公の予算でつくった学校ではない。田中壽一先生が私生活も切り詰めて立志された学校だ。我々の力で学校をつくるべきだと思っていた」。稲垣さんは当時の心境を農学部「三十年の歩み」(1980年刊)でつづっています。
神、仏があるならば
1951年10月19日「名城大学新聞」に、「大学諸設備の不十分を嘆く」という記事が掲載されました。
われわれは1年あるいは2年前、学問への若き情熱を胸に、喜びと希望に満ちてこの名城大学に入学した。しかし、この喜びと希望は今消え去ろうとしている。あの茫大なる農学部は五尺に余る葦の蔭に狐が遊び、兎が戯れ、そそり立つ時計は正に魔の巣窟のように見える。
また、地の利を得て延びんとしている理工学部校舎は、外部の子供の遊園地となり、朝夕、塀はおろか校舎まで破壊し、隣近のかまどの煙と化している。また、学園の街・昭和区に、幾棟の校舎と堂々たる講堂を有する法商学部の建物は一雨ごとに柱は朽ち、かつて優秀なる心身鍛錬の場であった運動場は草がのび、浅沼が散在し、蛙と蛇の闘争が繰り返されている。
われわれはこの現状を何とみるか。われわれの学園は実質的に存廃の岐路に立っているのだ。学長は優秀なる頭脳をもって十二分に本大学を他の大学に優るとも劣らぬ大学にせんがため努力している。しかし、その努力はわれわれ学生生活の向上のためではないといふとことは、以上の点で断言できる。この貧弱なる学内施設を何とみるか。これが中部随一を誇る名城大学と言えるか。われわれは過去6ヶ月有余、平身低頭して大学当局にこの問題につき建設的な意見を提出。特に夏期休暇においては、あるいは鷹来の農学部に、あるいは新富の理工学部に、駒方の法商学部にほとんど毎日登校し、実地調査を完了、現状を報告。これが早急完備の要請を行うこと十数回。しかし、その効ほとんどなく、この涙ぐましい学生の要望は、得意な饒舌と経済的苦痛を盾にその完備を怠ってきた。
ああもし神というものが存在し、仏というものがあったとしたら、この弱き小さな学生の血の叫びをいかに聞き、怠慢なる学校当局をいかに裁くであろうか――。
絞頭数学の妙味
同じ日付の「名城大学新聞」の別ページには短期大学部の授業の様子も「絞頭数学の妙味」の見出しで紹介されていました。
短期大学部商学科1年では人員に対する教室の矮小、それに加え備品の不足を訴えている。一個の机に4~5人が座り、筆記も容易でない今の現況であり、試験日ともなれば人員の増加は必定であり、それに関する学校当局の誠意ある措置が望まれている。例え教師の問題があろうと、それは単なる逃避的な字句にすぎず、現在そうした状況に置かれたクラスの存在こそ重大視しなければならないだろう。
庶民派「寿一っつぁん」
1951年、駒方校舎の法商学部商学科3期生として入学した桂川澈三さんが商学部創立30周年記念誌『碑』(いしぶみ)に書いた「草創の門」。第2部第1回で紹介した部分からの続きです。
「目的が明確に把握されていなければならず、明徳を明らかにする事であり、光を出さしむるために、学問を得することである」。創立者田中寿一先生の、耳なれた言葉がこれであった。熱烈な意気とでもいえようか、小さな体から発するその声と表情には、如何なる場合にも厳しいものがあった。
入学時、この地方での私立大学は、名城大のほか南山大、愛大、女子系では金城学院大、椙山女学園大など、その数においては関東、関西に比べ極めて少数といえた。名城大学が、戦後24年4月、いち早くスタートしたのも、創立者の熱烈な意気が物語るものと考えられてよかった。新制というよりは、新星であった。いつのときも、書籍を掌に、険しい表情で行動される姿に、何か近寄り難いものがあったが、一面において、どんこ列車を愛し、気軽に話しかけてこられた田中寿一先生の庶民性に対し、ぼくらは寿一っつぁんと呼び、人間形成への何かを感じていた。
(広報専門員 中村康生)